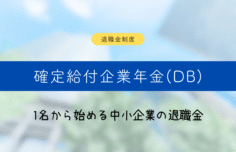中小企業の退職金相場【2025年版】導入率・制度設計ガイド
中小企業の経営者にとって、退職金制度は重要な課題です。退職金の相場はどのくらいなのか、自社に適した制度をどう設計すれば良いのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、企業規模、業種、役職ごとの退職金の相場や、退職金制度を設計する上での重要なポイントを解説します。適切な退職金制度を構築し、従業員のモチベーション向上と企業の持続的な成長を目指しましょう。
目次
1 退職金制度を導入する目的
まずは、退職金制度の導入目的を明確にしましょう。導入目的が明確になることで、制度設計の方向性が定まり、自社に最適な制度を構築できます。また、制度運用の効果測定や見直しの基準ともなります。

退職金制度の定義と役割
<退職金制度の定義>
退職金制度とは、企業が従業員の退職に際し、あらかじめ社内規程等に基づいて金銭(一時金または年金形式)を支給する仕組みです。主に長年の勤務に対する功労報奨や退職後の生活保障を目的としています。
法律による一律の義務はなく企業の任意制度ですが、就業規則等で定めれば企業は支払義務を負います。
<退職金制度の役割>
退職金制度は、従業員と企業の双方にとって多岐にわたる重要な役割を担います。
<従業員にとっての主な役割>
「生活保障」 退職後の生活資金を確保し、経済的な安定と将来への安心感を提供します。
「功労報奨」 長年の企業への貢献に対する報酬であり、達成感や満足感に繋がります。
「キャリア支援」 新たなキャリアへの挑戦や学び直しなど、セカンドライフの活動資金となり得ます。
<企業にとっての主な役割>
「人材戦略」 優秀な人材の獲得と長期的な定着(リテンション)を促進し、採用競争力を高めます。
「組織活性化」 従業員の勤労意欲や企業への忠誠心を高め、生産性向上に貢献します。
「円滑な組織運営」 計画的な人員の新陳代謝を促し、円満な退職をサポートします。
このように、退職金制度は従業員の福祉向上と企業の持続的成長を支える、労使双方にとって意義深い制度と言えます。
退職金制度の導入メリットと人材戦略上の位置づけ
企業が退職金制度を導入することにより、多くのメリットが期待できます。
<退職金制度導入の主なメリット>
・長期的な勤続インセンティブによる従業員のモチベーション向上
・魅力的な福利厚生として、優秀な人材獲得力の強化
・帰属意識が高まることによる定着率向上、離職率低下
・円満な退職を促し、計画的な世代交代による企業の新陳代謝向上
・従業員を大切にする企業としてのイメージアップ、企業の社会的評価向上
このように、退職金制度は単なるコストではありません。
採用、育成、定着といった人材戦略の各段階において、企業の競争力を高めるための戦略的ツールとして位置づけられます。
退職金制度を導入しない場合にとるべき対応
退職金制度がない場合、企業の採用競争力と従業員定着率に影響が生じます。
<採用競争力>
特に安定志向の強い層や長期キャリアを考える求職者にとっては魅力が薄れ、他社との比較で見劣りする可能性があります。
そのため、例えば一部のITベンチャーや成長企業では、退職金制度を設けない代わりに、高い年俸やストックオプション、あるいは成果に応じたインセンティブでこれを補い、異なる魅力を訴求するケースが見られます。
<従業員定着率>
長期勤続に対するインセンティブが欠けるため、社員の流動性が高まる可能性があります。
そこで、キャリア成長の機会、挑戦的な仕事内容、フラットな組織文化など、他の要素でエンゲージメントを高め、定着を図る必要があります。
総じて、退職金制度がない場合、それを補うだけの魅力的な報酬体系や企業文化、成長機会の提供が必要となります。
2 退職金の相場と実態データ
退職金の相場は業界や企業規模、地域によって大きく異なります。
掛金等の平均的な金額や背景を知ることで、企業は適正な財務負担を計画しすることができます。
また、制度の設計や導入時に、従業員の納得感を高める重要な判断材料となります。
【企業規模・勤続年数別】退職金相場(令和6年版)
企業規模別および勤続年数別の平均的な退職金額と、その傾向については次のとおりです。
<企業規模・勤続年数別 平均退職金支給額(大学卒)>
| 勤続年数 | 大企業 | 100~299人の企業 | 20~99人の企業 | 10~49人の企業 |
|---|---|---|---|---|
| 10年 | 305万円 | 160万円 | 132万円 | 145万円 |
| 15年 | 585万円 | 302万円 | 222万円 | 255万円 |
| 20年 | 1021万円 | 498万円 | 356万円 | 403万円 |
| 25年 | 1487万円 | 755万円 | 482万円 | 629万円 |
| 30年 | 2054万円 | 1026万円 | 661万円 | 758万円 |
| 定年 | 2858万円 | 1445万円 | 1096万円 | 1088万円 |
このデータから、基本的には企業規模が大きいほど、また勤続年数が長いほど退職金支給額は高くなる傾向があります。
大手企業と中小企業では、財務体力や導入している退職給付制度(例えば、企業年金制度の有無やその手厚さ)の違いが、支給額の差に繋がっているようです。
ただし、これらはあくまで平均値であり、個々の企業の制度、退職事由、最終学歴、役職などによって実際の支給額は大きく異なります。
※大企業:資本金5億円以上、従業員数1000人以上の企業(出典 厚生労働省中央労働委員会「令和5年賃金事情等総合調査」)
※中小企業:従業員数299人以下の企業(出典 東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」)
【業種別】中小企業退職金相場ランキング(令和6年版)
中小企業における業種別の退職金相場をランキング形式でご紹介します。
<業種別 平均退職金支給額(定年時、大学卒の数値順)>
| 業種 | 大学卒 | 高校卒 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 金融業、保険業 | 1940万円 | 1497万円 | |
| 教育、学習支援業 | 1244万円 | – | |
| 卸売業、小売業 | 1239万円 | 880万円 | |
| 情報通信業 | 1192万円 | 941万円 | ※令和4年データ |
| 製造業 | 1107万円 | 1027万円 | |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 1054万円 | 1205万円 | |
| 不動産業、物品賃貸業 | 1012万円 | 513万円 | ※令和4年データ |
| サービス業(その他に分類されないもの) | 969万円 | 1213万円 | |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 964万円 | 1026万円 | ※令和4年データ |
| 運輸業、郵便業 | 938万円 | 966万円 | |
| 建設業 | 929万円 | 991万円 | |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 358万円 | 281万円 | ※勤続20年データ |
| 医療、福祉 | 342万円 | 332万円 | ※令和4年データ |
このデータから、業種ごとに大きな差があることが分かります。
「金融業、保険業」はとびぬけて高く、「医療、福祉」は非常に低い傾向にあります。
また、「宿泊業、飲食サービス業」はデータ自体が少なく、勤続20年での情報しか掲載されていませんでした。金額も低いことから、退職金制度の整備があまり進んでいない業種といえます。
出典 東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」
東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)」
自社の退職金の支給額水準を確認しよう
ご覧のとおり、退職金の支給額は、企業規模や業種、学歴などによって大きな差が生じています。
退職金制度の充実度は、競合他社との採用競争、従業員の定着率に影響を与える重要な要素です。
企業は自社の退職金制度が業界内でどのような位置づけにあるのかを把握し、競争力を維持するための改善策を検討する必要があります。
退職金相場から考える適正な退職金制度の設計
退職金の相場は、企業規模や勤続年数、業種によって大きく変動します。
相場より高い水準で退職金制度を設計すると、採用競争力を高め、定着率が向上につながるメリットが生まれます。
ただし一方で、企業の財務状況にも影響するため、退職金制度の設計には慎重な検討が必要です。このことは、退職金制度がなかなか中小企業に普及しきれない課題ともいえるでしょう。
そこで、おすすめしたいのが、選択制の退職金制度である「YUKINつみたてDBプラン」です。
この制度は、退職金の積み立てを従業員それぞれの判断に委ねる制度です。
企業としては、退職金の相場や、給与と退職金のバランスを考える必要がありません。(退職金原資は制度導入前の給与を使用します。)
また、従業員の給与にかかる税金や社会保険料負担(労使両方)が減少する副次的効果が発生するメリットがあります。
従業員数数名の企業でも、厚生年金保険の適用事業所であれば、導入することが可能です。

3 退職金額を決定する主要素
退職金額は企業の規模、業界、勤続年数、職種、学歴、退職理由など複数の要素によって決まります。
そのうち、社内での主要素について、いくつかご紹介します。
勤続年数|なぜ重要視されるのか
退職金は勤続年数に応じて増加することが一般的です。
実際、多くの退職金制度では、勤続年数が計算の基礎となったり、支給率やポイントに影響を与えたりします。
しかし、そもそもなぜ、勤続年数が退職金制度上、重要視されるのでしょうか?
それは、主に以下の理由からです。
・長年の功労に対する報い
・長期の人材定着
・老後資金の形成
・勤続年数に応じた税制優遇(退職所得控除)
これらは、日本の長期雇用慣行とも関連が深く、制度設計の基本となっています。
具体的な増加率の傾向を把握するには、今回ご紹介した公的統計や、民間の調査データなどを参照するるといいでしょう。
自己都合・会社都合|市場相場と法的リスク
企業として、「自己都合」と「会社都合」の退職区分は正確な判断が不可欠です。
<自己都合退職>
自己都合退職とは、本人の意思による退職で、退職金は社内規程に基づき計算します。
<会社都合退職>
会社都合退職とは、事業縮小や解雇など企業側の理由であり、退職金規程での上乗せや解雇予告手当の支払いが生じ得ます。また、従業員への説明義務も伴います。
「市場相場」として一律の基準はありませんが、会社都合の場合に手厚くする慣行は見られます。しかし、安易な会社都合は失業保険料率への影響や特定の助成金対象外となる経営リスクを伴います。
なお、不当な理由での会社都合扱いや、自己都合への偽装は、従業員からの訴訟や労働基準監督署からの指導など、企業にとって重大な法的リスクと信用の失墜を招きます。
退職事由の判断と対応は、規程に基づき公正かつ慎重に行う必要があります。
役職・等級|退職金テーブル作成時のポイント
退職金テーブルに役職や等級を組み込むことは、社員の貢献度を反映させ、納得感を高める上で有効です。設計時の主なポイントは以下の通りです。
<算定方法>
役職・等級を反映しやすいのは、功績倍率方式(役職別に倍率設定)やポイント制です。
<人事制度との連携>
等級定義と退職金テーブルの整合性を取り、社員が昇給・昇格と退職金の関連性を理解できるようにします。
<テーブルの公平性と透明性>
勤続年数と役職・等級、それぞれの貢献をどうバランスさせるか調整します。
<会社の財務状況>
支払い能力を超えない、持続可能な制度設計が必要です。
これらのポイントを踏まえ、自社に最適なテーブルを作成しましょう。
4 退職金計算方法の違いと設計ポイント
退職金の計算方法には様々な方法があり、企業の人材戦略、財務戦略に応じて選択されます。
一般的な制度の設計方法のポイントを整理します。
基本給連動型|最終基本給と勤続年数で計算
基本給連動型の退職金制度は、多くの企業で伝統的に使われる計算方法です。退職時の基本給を基に、勤続年数に応じた計算で退職金額を決めます。シンプルですが、退職時の基本給が退職金に大きな影響を与えます。
<基本の計算式>
退職金 = 退職時の基本給 × 勤続年数別支給率 × 退職事由係数
<メリット・デメリット>
・シンプルで分かりやすい
・賃金体系との連動性が良い
・将来の基本給上昇が読みにくく、退職金コストの見通しが立てにくい場合がある
・基本給が年功的に上昇する場合、必ずしも個人の業績や貢献度が反映されない可能性がある
<設計の重要ポイント>
支給率テーブルの設定は慎重に行い、会社の支払い能力や他の人事制度との整合性を考慮することが重要です。
定額制|勤続年数に応じて金額が固定
定額制の退職金制度では、勤続年数に応じて、あらかじめ定められた一定額を退職金として支給します。個々の基本給や評価に左右されません。
例えば、勤続10年なら100万円、勤続20年なら250万円のように、勤続年数ごとに定めます。
<基本の計算式>
退職金 = 勤続年数に応じた定額
<メリット・デメリット>
・非常に分かりやすく、計算の必要がない
・コストの予測が容易
・個人の業績や評価を反映できない
・インフレに対応できない
<設計の重要ポイント>
勤続年数ごとの定額テーブルの設定が全てです。相場や会社の支払い能力を考慮し、自社の賃金・人事制度全体とのバランスを見て金額を決定する必要があります。定期的な金額の見直しも検討しましょう。
ポイント制|勤続・貢献度などをポイントで計算
ポイント制の退職金制度とは、従業員に対し、勤続年数、役職・等級、人事評価などに応じてポイントを付与し、退職時に累計ポイント合計に単価を乗じて退職金額を算出する方法です。ポイントの付与基準や単価は会社が独自に定めます。
<基本の計算式>
退職金 = 累計付与ポイント × ポイント単価 × 退職事由係数
<メリット・デメリット>
・役職や評価をポイント化できるため、業績や貢献度を反映しやすい
・会社の評価制度や経営状況にあわせて、ポイント付与基準や単価を調整しやすく、柔軟な制度設計が可能
・ポイント単価の調整等でコストコントロールできる
・他の制度より複雑になる可能性がある
・従業員に分かりやすく説明をすることの難易度が高くなる
<設計の重要ポイント>
どのような要素にどれだけポイントを付与するか、そしてポイント単価をいくらにするかが設計の核となります。評価制度との連携や、従業員への丁寧な説明が成功の鍵となります。
別テーブル制|基本給と別の基礎金額テーブルで計算
別テーブル制の退職金制度とは、給与制度とは切り離し、役職や職種等ごとに独自の基礎金額テーブルを用いて退職金を計算する方法です。基本給等の変動に直接影響されず、役職や等級に紐づく形で退職金が決まります。
<基本の計算式>
退職金 = 基礎金額(役職・等級等) × 勤続年数別支給率 × 退職事由係数
<メリット・デメリット>
・基本給改定の影響を受けにくい
・基本給連動型と比べ、将来の退職金コストの予測が比較的容易
・「役職」「等級」を反映できる
・給与制度とは別の計算根拠となるため、従業員の制度理解の難易度が高い
・基礎金額テーブルと支給率テーブルの設定が適切でなければ、従業員の納得感が得られない可能性がある
<設計の重要ポイント>
役職や等級ごとの適切な基礎金額と、勤続年数別の支給率テーブルの設定が重要です。会社の等級制度やキャリアパスとの整合性を図りつつ、外部相場も参考に設計を進める必要があります。
5 退職金の税制優遇と会計処理
退職金は退職所得として扱われ、税金の軽減措置が適用されます。
退職所得控除による税制メリット
<退職所得控除>
退職所得控除とは、退職金にかかる税金負担を軽減するための税制上の優遇措置です。勤続年数に応じて控除額が増える仕組みになっており、退職所得からこの控除額を差し引いた金額に対して税金がかかります。
<従業員のメリット>
退職金にかかる税金(所得税・住民税)が大幅に軽減され、手取り額が増加します。
退職金は「退職所得控除」が適用され、さらに他の所得(給与など)とは別に分離課税されます。これにより、給与として受け取る場合に比べて所得税・住民税の負担が大幅に軽減され、結果として従業員の手取り額が増加します。
同じ総額の報酬を支払う場合でも、税引き後の手取り額が多くなるため、従業員にとっては退職金での受け取りが有利になることが多いです。
<企業のメリット>
従業員側の税負担が軽いということは、企業が提供する報酬パッケージ全体の魅力向上に繋がります。
単に給与を上げるよりも、退職金制度を充実させる方が、従業員の税負担軽減という形でより大きな実質的なメリットを提供できる可能性があります。
これは、優秀な人材の採用や離職防止において有利に働く要因となります。
退職金の税金計算と手取り額シミュレーション
退職金にかかる所得税・住民税は、毎月の給与とは別に計算される「分離課税」となり、税負担が優遇されています。
<退職所得の計算方法>
税金の計算対象となる「課税退職所得金額」は、以下の式で計算されます。
課税退職所得金額 = (退職金の収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
ここでの大きな特徴は、退職所得控除を差し引いた後にさらに金額が半分になる点です。(1/2課税)
退職所得控除額とは、勤続年数に応じて、以下の通り計算される非課税となる金額です。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年) |
<手取り額シミュレーション(例)>
例:勤続25年、退職金2,000万円の場合
退職所得控除額:800万円 + 70万円 × (25年 – 20年) = 1,150万円
課税退職所得金額:(2,000万円 – 1,150万円) × 1/2 = 425万円
この425万円に所得税・住民税の税率をかけて税額が計算されます。控除と1/2課税により、退職金全額ではなく、大幅に圧縮された金額に対してのみ課税されるため、税負担が軽減され、手取り額が増える仕組みです。
なお、詳細は国税庁のHPで確認できます。
参考URL:国税庁HP「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
税務調査で注意すべき退職金関連のポイント
税務調査では、退職金が適正に処理されているかが確認されます。特に重要なのは以下の点です。
・「退職」の実態:特に役員の場合、形式的な退任でなく、経営への関与が実質的に終了しているかが厳しく見られます。
・支給額の合理性:従業員、特に役員への退職金が、会社の規程や功績、同業他社の水準と比べて不相当に高額でないかを確認されます。
・手続きと書類:就業規則・退職金規程に基づく決定か、株主総会議事録など、適正な手続きと証拠書類があるかが重要です。
・損金算入時期:退職金を会社の経費として計上する時期が正しいかも確認対象です。
これらを踏まえ、規程整備と適切な処理が不可欠です。
6 退職金の支給形態の違い
退職金には主に二つの主要な支給形態があります。企業は、これらの支給形態が持つ特性を理解し、制度設計や資金準備、情報提供を行うことが重要です。
また、従業員は自身のライフプランや税務上の影響を考慮し、企業が定める制度の中で最適な方法を選択することになります。
一時金支給(一括支給)のポイント
退職時に、退職金の全額を一度にまとめて支給します。
<企業側>
資金準備:退職者が出る都度、まとまった資金を準備する必要があります。
税務・社会保険:支払額は損金算入でき、社会保険料の算定対象とはなりません。
管理:支払いが一度で完結するため、その後の継続的な管理事務は発生しません。
<従業員側>
税制優遇:退職所得控除が適用され、さらに課税対象額が1/2になるなど、税負担が大きく軽減される可能性が高いです。手元にまとまった資金が入るため、住宅ローンの一括返済や大きな支出、新たな投資などに充てやすい利点があります。
資金管理の必要性:多額の資金を自身で管理・運用する責任が生じます。計画的に使わないと早期に資金が底をつくリスクや、運用に失敗するリスクも伴います。
年金支給(分割支給)のポイント
退職後、退職金を一定期間にわたって定期的な「年金」として受け取る方法です。主に企業年金制度などでこの形式が採用されています。
<企業側>
資金負担の平準化:支払いが分散されるため、企業の財務負担が平準化されます。
継続的な管理:年金の支払いが続く期間は、継続的な管理事務が発生します。
<従業員側>
収入の安定:定期的に収入が得られるため、長期的な生活設計が立てやすくなります。
税務・社会保険:雑所得として公的年金等と合算して課税されることが多く、一時金ほどの税制優遇は一般的にありません。
インフレリスク:物価上昇に伴うインフレリスクを考慮する必要があります。
退職金と社会保険・在職老齢年金の関係性|実務担当者必見のポイント
退職一時金は「労働の対価」である給与や賞与とは区別されるため、原則として社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)の算定対象にはなりません。
また、60歳以降に働きながら老齢厚生年金を受け取る「在職老齢年金制度」において、年金額が調整されるかどうかの判断には、毎月の「基本月額(年金月額)」と「総報酬月額相当額(給与や賞与を基に計算)」の合計が基準となります。
このとき、退職一時金はこの「総報酬月額相当額」や年金額には含まれません。
したがって、退職一時金を受け取っても、それが直接の原因で在職老齢年金が減額されることはありません。
ただし、退職金を年金形式で受け取る場合は、その年金額が雑所得として扱われ、年金収入として在職老齢年金の計算に影響する可能性があります。
7 退職金制度を持たない企業の代替戦略
退職金制度を持たない企業は、給与や福利厚生の充実、従業員持ち株制度の導入など、代替戦略を活用することで人材定着と満足度向上を図ることが可能です。
YUKINつみたてDBプラン|様々なニーズに対応できる選択制退職金制度
YUKINつみたてDBプランとは、複数の企業が共同で運営する総合型確定給付企業年金制度です。
従業員一人一人、自ら指定した金額を退職金として積み立てることができます。積立金は、退職時だけでなく、休職時に受け取ることができます。
<メリット>
・企業は退職金の原資を新たに用意する必要がない。(制度導入前の給与原資を使用)
・掛金は全額損金算入可能。
・掛金は1000円単位で指定し、定期的に変更できる。
・従業員は、給与にかかる税金や社会保険料の負担が軽減する。
・法定福利費負担が減少することがある。
・役員も加入できる。
<デメリット>
・社会保険料負担が減少する場合、社会保障給付が減少する影響がある。
・従業員にしっかりと制度説明をしなければならない。
▼詳しくは、こちらをご覧ください▼

中小企業退職金共済制度|国や自治体が運営する共済制度
中小企業退職金共済(中退共)は、国が運営する中小企業向けの退職金制度です。企業が毎月掛金を納付し、従業員が退職した際に中退共から退職金が支払われます。また、導入には、一定の要件があります。
<メリット>
・企業で退職金制度を管理する負担が少ない。
・掛金は全額損金算入可能。
・従業員は企業が倒産しても退職金を受け取ることができる。
<デメリット>
・個別の貢献度などを反映しにくく、制度設計の柔軟性は低い。
・短期間の退職(2年未満)は元本割れとなる可能性がある。
・役員は加入できない。
詳細はこちらを確認してください。
参考URL:中小企業退職金共済事業本部
iDeCo+(イデコプラス)|従業員の自助努力を支援
iDeCo+は、企業年金を実施していない従業員300人以下の中小企業が、iDeCoに加入している従業員の掛金に上乗せして拠出できる制度です。
<メリット>
・企業型確定拠出年金(企業型DC)よりも導入・管理が容易。
・拠出額は全額損金算入可能。
<デメリット>
・対象はiDeCo加入者のみ。
・拠出額に上限がある。
詳細はこちらを確認してください。
参考URL:iDeCo公式サイト
8 退職金制度の最新トレンドと将来展望
日本の多くの企業で導入されている退職金制度は、かつての「終身雇用・年功序列」という働き方を前提としたものから、社会経済情勢や多様化する雇用形態に合わせて大きく変化しつつあります。
この変化を理解することは、企業にとっても働く人々にとっても、今後のキャリアや経営を考える上で大変重要です。
多様化する制度形態
以前は、退職時にまとめて支払われる一時金や、企業が運用責任を持つ確定給付企業年金(DB)が中心でした。
しかし、転職が一般的になったことや、企業側の運用リスク管理の観点から、従業員自身が運用する確定拠出年金(DC)の導入にシフトしていきました。
ただし、DCは60歳以降でなければ受け取ることができないため、DBとDCを併用する企業等も存在しています。
従業員の選択と自助努力を重視
制度の設計において、従業員が自らの意思で選択できる「選択制」の考え方が広がっています。給与の一部を退職金として積み立てるか、そのまま受け取るかなどを従業員が決められる制度があります。
また、企業の支援を受けながら個人で老後資金を作るiDeCo+のような仕組みも登場しています。これは、従業員の自助努力を促し、個人の資産形成を後押しする流れと言えます。
「選択制DB」という新しい流れ
確定給付型の安定性と、確定拠出型の柔軟性や従業員の選択を取り入れた「選択制DB」という制度も出てきています。
選択制DB(YUKINつみたてDBプラン)は、基本的な給付はDBの仕組みで行いつつ、従業員が任意で掛金を追加で積み立てられる特徴を持ちます。
リスクの少ない運用方針で、企業が一定の給付を保証しながらも、従業員の多様なニーズや資産形成の意欲に応える、新しいハイブリッドな制度として注目されています。

よくあるご質問
退職金制度を導入する主な目的は何ですか?
退職金制度は、従業員の退職後の生活保障や長年の功労への報奨、キャリア支援などの役割を果たします。企業にとっては、優秀な人材の獲得・定着、従業員のモチベーション向上、円滑な世代交代促進、企業イメージアップといった人材戦略上の重要なメリットがあります。
退職金額を決定する主な要素は何ですか?
退職金額は、主に勤続年数、退職理由(自己都合か会社都合か)、役職・等級によって決まります。勤続年数が長いほど、また会社都合退職や高い役職であるほど、支給額が優遇されるのが一般的です。
退職金には税金がかかりますか?税制優遇はありますか?
はい、退職金には所得税と住民税がかかりますが、「退職所得控除」という大きな税制優遇が適用されます。勤続年数に応じた控除額が設定されており、控除後の金額の半分にしか課税されないため、通常の給与所得に比べて大幅に税負担が軽減されます。