福利厚生費のすべて:税務・経理・戦略的活用まで徹底解説
2025年5月8日
企業が従業員の働きやすい環境を整えるために活用する「福利厚生費」。
これを戦略的に設計することで、税務負担を適正化しながら従業員満足度を高めることが可能です。
本ブログでは、福利厚生費の基本概念から、法定福利費と法定外福利費の違い、税務処理のポイント、成功事例までを幅広く解説します。
適切な管理を行い、企業の持続的成長を支える福利厚生制度の構築に役立ててください。
目次
1 福利厚生費の基本知識
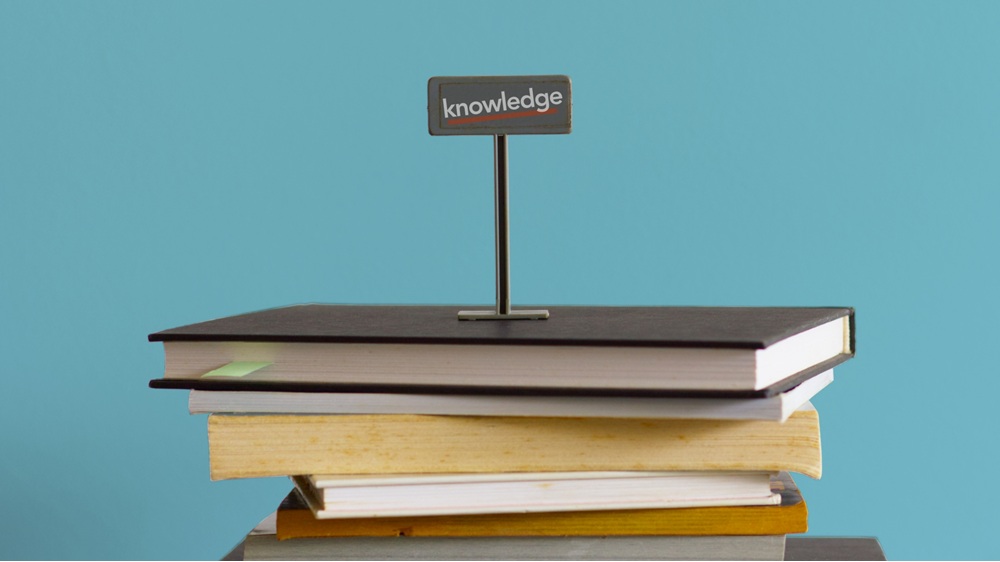
福利厚生費とは、企業が従業員のために給与や賞与以外に支出する費用です。従業員の満足度向上や人材確保に繋がる経費とされています。
法定福利費(社会保険料など法律で定められたもの)と、法定外福利費(住宅手当、社員旅行、レクリエーション費用など企業が独自に定めるもの)があります。
1-1福利厚生費とは?経理・税務上の定義と位置づけ
福利厚生費は、従業員の労働意欲の向上や定着促進を目的とした費用として認識されます。
勘定科目としては「福利厚生費」が用いられ、給与や旅費交通費などとは区別されます。従業員全体を対象とした、社会通念上妥当な金額の支出が原則です。
税務上では、福利厚生費は一定の要件を満たす場合に損金として扱われます。
主な要件として、
・全従業員が対象であること
・金額が社会通念上相当であること
・現金支給でないこと
などが挙げられます。
また、福利厚生費は、法定福利費(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など法律で定められたもの)と、法定外福利費(住宅手当、通勤手当、社員旅行、慶弔見舞金、食事補助など企業が任意で定めるもの)に分類されます。
法定福利費は企業負担分が全額損金となり、法定外福利費は、上記の要件を満たすものが損金として認められます。
福利厚生費の適切な管理と計上は、従業員の満足度向上と企業の節税対策の両面から重要となります。
1-2企業が福利厚生費を支出する戦略的目的と効果
企業が福利厚生費を支出するのは、従業員の満足度を向上させると同時に、組織の競争力を高めるための戦略的な取り組みです。
福利厚生は、従業員の健康や生活の充実を支援し、職場環境を改善する役割を果たします。これにより、離職率を低下させ、優秀な人材の確保や維持が可能となります。
また、福利厚生費を活用することで従業員のモチベーションを向上させ、生産性の向上につながる効果も期待できます。
さらに、福利厚生を充実させた企業は、社会的責任を果たす姿勢を示し、企業イメージの向上や信頼の構築にも寄与します。
福利厚生費は、企業と従業員双方に利益をもたらす重要な投資と言えるでしょう。
1-3福利厚生費の対象範囲と従業員区分別の取扱い
福利厚生費の対象範囲は、原則として全従業員とその家族に及ぶ場合があります。正社員だけでなく、契約社員、パート・アルバイト、派遣社員なども対象となることが重要です。
従業員区分別の取扱いの要点は以下のとおりです。
幅広い福利厚生制度が適用されることが一般的です。住宅手当、通勤手当、家族手当、社員旅行、レクリエーション費用などが該当します。
【非正規社員(契約社員、パート・アルバイト、派遣社員など)】
法令や企業の規定に基づき、合理的な範囲で福利厚生が提供される必要があります。
同一労働同一賃金の原則の観点から、正社員との不合理な差を設けることは避けられるべきです。
通勤手当や食事補助など、業務に関連性の高い福利厚生は特に考慮が必要です。
【役員】
従業員と同様の福利厚生が認められる場合もありますが、過度なものは給与とみなされる可能性があります。税務上の判断が重要になります。
重要なのは、特定の従業員のみを対象としたり、不合理な差を設けたりしないことです。
全従業員が公平に利用できる福利厚生制度を設計することが、従業員のモチベーション向上や企業イメージの向上に繋がります。
ただし、福利厚生の内容によっては、その性質上、対象となる従業員区分が限定される場合もあります。
2 福利厚生費の分類と具体的な費目
福利厚生費は法定福利費と法定外福利費に分類されます。それぞれの特徴や違いについてご紹介します。
2-1法定福利費の範囲と留意点
法定福利費とは、法律で企業が加入・負担することが義務付けられている社会保険料などの費用です。主な範囲は以下のとおりです。
| 健康保険・介護保険料 | 従業員やその家族の医療費などを保障する保険料で、労使で折半負担が原則。40歳以上は介護保険料も徴収される。 |
| 厚生年金保険料 | 従業員の老後の所得保障となる年金保険料で、労使で折半負担が原則。 |
| 雇用保険料 | 従業員の失業時の給付や再就職支援、育児休業給付などに充てられる保険料。労使で負担割合が異なる。 |
| 労災保険料 | 従業員の失業時の給付や再就職支援、育児休業給付などに充てられる保険料。労使で負担割合が異なる。 |
| 子ども・子育て拠出金 | 児童手当などの子育て支援の費用に充てられる拠出金で、全額事業主負担です。 |
留意点として、保険料率や計算方法は年度や地域、業種によって異なる場合があります。正確な保険料率を確認し、適切に計算・納付する必要があります。
また、従業員の加入状況に変更があった場合は、速やかに手続きを行う必要があります。法定福利費の未払いや不適切な処理は、法令違反となる可能性があるため注意が必要です。
2-2法定外福利費の種類と税務上の取扱い
法定外福利費は、法律で義務付けられていない企業独自の福利厚生制度にかかる費用です。種類は多岐に渡りますが、主なものとして以下が挙げられます。
| 住宅関連 | 住宅手当、家賃補助、社宅の提供など |
| 通勤関連 | 通勤手当(一定額まで非課税)、送迎バスの運行など |
| 健康・医療関連 | 健康診断、人間ドック費用補助、医療費補助、カウンセリングサービスなど |
| 慶弔・災害関連 | 結婚祝い金、出産祝い金、弔慰金、災害見舞金など |
| レクリエーション関連 | 社員旅行、運動会、クラブ活動補助、レジャー施設利用補助など |
| 自己啓発・能力開発関連 | 研修費補助、資格取得支援など |
| 食事関連 | 食事手当、社員食堂・給食費補助など |
| 育児、介護支援関連 | 託児所設置・利用補助、育児・介護休業給付金の上乗せなど |
税務上の取扱いとして、これらの費用は原則として損金算入が認められます。ただし、以下の点に留意が必要です。
①全従業員が対象であること・・・特定の従業員のみを対象とした場合は、給与とみなされる可能性があります。
②社会通念上相当な金額であること・・・過度な支出は損金として認められない場合があります。
③現金支給でないこと・・・現金で支給する場合は、原則として給与課税の対象となります。
④福利厚生の目的が明確であること・・・従業員の福利厚生を目的とした支出であることが重要です。
適切な制度設計と運用により、法定外福利費は従業員の満足度向上や企業イメージの向上に貢献し、かつ税務上のメリットも享受できます。
2-3給与課税される福利厚生費と非課税となる福利厚生費の線引き
給与課税されるか非課税となるかの線引きは、福利厚生費が「現金支給」か「現物支給」か、そして「全従業員が対象か」「社会通念上妥当な金額か」が主な判断基準です。
| 原則として課税されるもの | 原則として非課税となるもの |
|---|---|
| 現金支給 例) -住宅手当 -家族手当 -通勤手当(一定額超) -慶弔金(社会通念上過大) | 現物支給かつ全従業員が対象で 社会通念上妥当なもの 例) -通勤手当(一定額までの交通機関利用料等) -食事補助(従業員が半額以上負担等一定の条件を満たす場合) -社員旅行・レクリエーション (全従業員対象で、社会通念上妥当な範囲内) -現物による慶弔品(お祝い金品、香典など) -健康診断(全従業員が対象で、一般的な範囲内) |
<注意点>
※一部課税、非課税のケース: 食事補助や通勤手当など、一定の条件や金額を超えると課税対象となる場合があります。
※特定の従業員のみ対象: 一部の従業員のみを対象とした現物支給は、給与とみなされることがあります。
※社会通念上の判断: 金額や内容が社会通念上逸脱している場合は、課税対象となる可能性があります。
2-4通勤費補助の福利厚生費計上と税務処理の実務
通勤費補助は福利厚生費として計上できますが、所得税法上、通勤手段・距離に応じた非課税限度額が定められています。
例えば、公共交通機関は月15万円まで、マイカー通勤は距離に応じて上限が定められています。そして、非課税限度額を超過する分は給与として課税(源泉徴収)が必要です。
税務調査では経路の合理性や非課税限度額の適用が確認されるため、従業員の通勤経路確認、非課税限度額の管理、規程整備は非常に重要です。
(参考) 国税庁HP
【電車・バス通勤者の通勤手当について】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
2-5慶弔見舞金の福利厚生費計上と社内規程の整備
慶弔見舞金は、社内規程に基づき、社会通念上妥当な金額であれば福利厚生費として計上できます。
規程を整備することで、公平な支給と税務上の適正な処理が可能になります。
【支給対象】従業員本人、配偶者、家族の範囲を明確化。
【支給事由】結婚、出産、弔事、傷病、災害などを具体的に規定。
【支給金額】慶弔の種類や従業員の勤続年数などで金額を定める。高額すぎると給与課税の可能性あり。
【申請手続き】申請方法や必要書類を定める。
【非課税限度額】税法上の非課税限度額を考慮した金額設定。
2-6福利厚生費と交際費の区分|判断ポイント(判断事例あり)
福利厚生費と交際費の明確な区分基準は、対象者と目的です。
・福利厚生費・・・従業員全体の福利厚生を目的とした費用。従業員の労働意欲向上や定着促進が目的。
・交際費・・・特定の取引先など事業関係者との親睦を深め、円滑な関係を築くための費用。事業遂行上の必要性が目的。
社員旅行(全従業員対象で、慰安目的が主) → 福利厚生費
取引先とのゴルフ(事業上の接待目的) → 交際費
従業員の慶弔見舞金(従業員対象の慶弔目的) → 福利厚生費
得意先への贈答品(事業関係者への贈答目的) → 交際費
社内レクリエーション(全従業員対象の親睦目的) → 福利厚生費
得意先との会食(事業上の打ち合わせを兼ねた接待) → 交際費
ただし、実質的な内容で判断されるため、名目が福利厚生費でも実質が接待であれば交際費とみなされることがあります。
少額な飲食費など、交際費に該当するか福利厚生費に該当するか曖昧な場合は、税務署や税理士に確認することが重要です。
2-7福利厚生費と会議費の区分|判断ポイント
会議費は、社内外の関係者が参加する業務上の会議・打ち合わせに要する費用です。参加者の主体は業務遂行に関わるメンバーであり、目的は意思決定や情報共有です。
一方、福利厚生費は、主に自社の従業員を対象とした、従業員の慰安・親睦・福利向上を目的とする費用です。参加者の主体は従業員であり、目的はモチベーション向上やコミュニケーション促進です。
参加者と目的を明確にすることで区分できます。業務関連性が高く社外関係者がいれば会議費、従業員向けで慰安目的が強ければ福利厚生費となります。
2-8福利厚生費と研修費の区分|判断ポイント
研修費は、従業の知識・技能向上を目的とした費用で、人材育成費として処理します。業務遂行に必要な研修費用や資格取得支援などが該当します。
一方、福利厚生費は、従業員の慰安・親睦・福利向上を目的とした費用です。
研修旅行など、両方の要素を含む場合は、主たる目的で区分します。
人材育成に関わる費用は研修費、従業員全体の福利厚生に関わる費用は福利厚生費として適切に処理しましょう。
税務上の取扱いはそれぞれ異なるため注意が必要です。
2-9要注意!福利厚生費として認められない費用と対応策
福利厚生費として認められない費用は、税務調査で否認される可能性があります。主な例と対応策は以下の通りです。
【認められない費用例】
特定の役員や従業員のみを対象としたもの。全従業員が公平に利用できる制度設計が必要です。
| 現金支給 | 原則として給与課税の対象。現物支給や補助の形に切り替えを検討。 |
| 社会通念上、過度に高額なもの | 金額設定は慎重に。同業他社の事例などを参考に適正な範囲に。 |
| 個人的な支出とみなされるもの | 私的な旅行費用や趣味の物品購入などは認められません。目的を明確にし、公私混同を避ける。 |
| 交際費とみなされるもの | 実質が取引先への接待である場合は交際費として処理。区分基準を明確化し、証拠書類を整備。 |
| 会議費とみなされるもの | 実質が従業員の慰安目的の場合は福利厚生費、業務上の会議であれば会議費として処理。 |
適切な運用と管理により、福利厚生費の否認リスクを低減できます。
・社内規程の整備:福利厚生の目的、対象者、支給基準などを明確に定める。
・全従業員への周知:制度内容を従業員に周知し、公平性を確保する。
・証拠書類の保管:領収書、参加者名簿、会議議事録など、支出内容を証明する書類を適切に保管。
・税務署・税理士への確認:判断に迷う場合は、事前に専門家へ相談する。
・定期的な見直し:社会情勢や税法の改正に合わせて、福利厚生制度を見直す。
3 福利厚生費の会計処理と経理実務

福利厚生費は、法定福利費と法定外福利費に分けて管理され、全従業員に公平に提供される必要があります。会計処理では、適切な科目分類と記帳が求められます。
3-1福利厚生費の損金算入要件と経費計上の基本ルール
福利厚生費の損金算入要件とは、企業が従業員の生活や職場環境の向上を目的とした支出を経費として認められる条件のことを指します。
主な要件は、公平性と合理性で、全従業員に対して公平に提供されることが求められます。
例えば、健康診断費用や社員旅行費用などが該当しますが、特定の従業員のみを対象とする場合や個人的利益が強い場合は、給与課税の対象となる可能性があります。
経費計上の基本ルールとしては、正確な記帳と税務上の適切な分類が必要です。
福利厚生費は「一般管理費」として仕訳されることが多く、関連資料の保存や社内規程の整備が重要です。これにより、税務リスクを回避し、企業運営の透明性を高めることが可能となります。
3-2福利厚生費の仕訳例
福利厚生費は、企業が従業員の福利向上を目的として支出する経費であり、適切な勘定科目の選択が重要です。一般的に「福利厚生費」勘定科目として処理されます。
例えば、社員旅行の費用は以下のように仕訳されます。
(借方)福利厚生費 100,000円
(貸方)普通預金 100,000円
また、一般的には、健康診断費用や通勤費補助なども福利厚生費に該当します。
適切な仕訳と記帳を行うことで、税務リスクを軽減し、企業運営の透明性を確保できます。判断に迷った場合には、顧問税理士等の専門家に助言を求めましょう。
3-3福利厚生費の課税・非課税判定
福利厚生費の課税・非課税の判定では、まず、対象となる支出が従業員全体に公平に提供されているかを確認します。
全従業員が利用可能な福利厚生(例: 健康診断費用や社員旅行費用)は、非課税として処理されることが一般的です。一方、特定の従業員に対する支給や個人的利益が強い場合は課税対象となる可能性があります。
実務対応としては、判定基準を明確化したフローチャートを作成し活用することで、現場での迅速な判断が可能になります。
また、税務申告時には記録や証拠書類を整備し、専門家の意見を参考に適切な対応を行うことが推奨されます。これにより、透明性の高い福利厚生費運用が実現します。
4 個人事業主における福利厚生費の取扱い
個人事業主では、福利厚生費として計上できる範囲が限られます。従業員への福利厚生費は認められますが、自身の支出は生活費とみなされ経費になりません。
4-1個人事業主が活用できる福利厚生費の範囲と必要経費算入の条件
個人事業主も福利厚生費を活用できますが、法人と異なり、自身への支出は経費計上できません。
福利厚生費として認められるのは、従業員や専従者(青色事業専従者)のための費用に限定されます。
例えば、健康診断費用、通勤費補助、慶弔見舞金などは、一定の条件を満たせば経費算入が可能です。
経費計上の条件として、公平性が求められ、事業に関連する必要があります。例えば、従業員全員に提供される健康診断費用は福利厚生費として認められますが、特定の従業員だけへの支給は給与扱いとなる可能性があります。
適切な運用と記帳を行い、税務リスクを回避することが重要です。社内規程の整備も有効な対策となります。
4-2家族従業員への福利厚生費支出時の税務上の注意点と対策
個人事業主が家族従業員へ福利厚生費を支出する際は、税務上の取扱いに注意が必要です。
福利厚生費として認められるためには、一般従業員と同様の基準で公平に提供されることが求められます。
例えば、健康診断費用や通勤補助を家族従業員にも同じ条件で提供していれば、福利厚生費として計上可能です。
しかし、特定の家族だけを対象とした場合、給与課税の対象になる可能性があります。
・対策として、社内規定を整備し、支給基準を明確化する。
・一般従業員と同じ条件で支給し、公平性を確保する。
・記録を残し、税務調査時の対応をスムーズにする。
適切な処理を行うことで、税務リスクを回避しつつ福利厚生を有効活用できます。
5 福利厚生費を活用した税務戦略

福利厚生費を活用することで、企業は税務負担を軽減しつつ従業員満足度を向上させることが可能です。全従業員に公平に提供される制度を設計し、適正な経費計上を行うことで、節税効果を最大化できます。
5-1法人税負担を適正化する福利厚生費活用の税務プランニング
福利厚生費を適切に活用することで、法人税の負担を軽減しながら従業員満足度を向上させることが可能です。
税務上、福利厚生費は経費として認められ、企業の法人税負担を抑える効果があります。
ただし、全従業員に公平に提供されることが条件となるため、規程の整備が重要です。
具体的なプランニングとして、社内規程を明確にし、健康診断費用、社員旅行、社内イベント費用などを戦略的に導入することで、節税と従業員の福利向上を両立できます。
また、税務リスクを避けるために、個人的な支出や特定の従業員のみを対象とする福利厚生は給与扱いとなる可能性があるため注意が必要です。適切な運用を行うことで、企業の財務戦略に貢献できます。
5-2税務メリットと従業員満足度を両立する福利厚生費の選択と設計
福利厚生費は、企業の税務負担を軽減しながら従業員の満足度を向上させる重要な要素です。
適切な設計を行うことで、節税効果を得つつ、従業員の働きやすい環境を整えることが可能です。
例えば、健康診断費用や通勤費補助は、全従業員に公平に提供されることで福利厚生費として認められ、法人税の負担軽減につながります。
また、選択型福利厚生制度(カフェテリアプラン)を導入することで、従業員が自身のニーズに応じた福利厚生を選択でき、満足度の向上が期待できます。
税務上のリスクを避けるためには、社内規程を整備し、適正な経費計上を行うことが重要です。
企業の成長と従業員の幸福を両立させるために、戦略的な福利厚生費の活用が求められます。
6 福利厚生費に関する税務調査対策と実務Q&A

福利厚生費は税務調査で指摘されやすい項目の一つです。
全従業員に公平に提供されているか、給与課税の対象にならないかを確認し、適切な記録を残すことが重要です。社内規程の整備と専門家の助言を活用し、税務リスクを回避しましょう。
6-1税務調査で指摘されやすい福利厚生費の事例と事前対策
福利厚生費を適切に計上するためには、証憑書類の整備と社内規程の明確化が不可欠です。
税務調査では、福利厚生費が交際費と誤認されるケースがあるため、支出の目的や対象者を明確に記録することが重要です。
例えば、社員旅行や社内イベントの費用は、全従業員が公平に参加できることを証明する書類が必要です。
証憑書類としては、開催通知、参加者名簿、領収書、支出内訳などを適切に保管し、税務調査時に説明できるようにしておくことが求められます。
また、社内規程を整備し、福利厚生費の対象範囲や支給基準を明確にすることで、税務リスクを軽減できます。適切な管理を行うことで、企業の透明性を高め、従業員の満足度向上にもつながります。
6-2経理担当者必見!福利厚生費計上時の証憑書類と社内規程整備
福利厚生費を適切に計上するためには、証憑書類の整備と社内規程の明確化が不可欠です。
税務調査では、福利厚生費が交際費と誤認されるケースがあるため、支出の目的や対象者を明確に記録することが重要です。
例えば、社員旅行や社内イベントの費用は、全従業員が公平に参加できることを証明する書類が必要です。
証憑書類としては、開催通知、参加者名簿、領収書、支出内訳などを適切に保管し、税務調査時に説明できるようにしておくことが求められます。
また、社内規程を整備し、福利厚生費の対象範囲や支給基準を明確にすることで、税務リスクを軽減できます。適切な管理を行うことで、企業の透明性を高め、従業員の満足度向上にもつながります。
6-3判断基準〜福利厚生費・交際費・経費の区分と実務上の処理
福利厚生費、交際費、経費の区分は税務上重要なポイントです。福利厚生費は従業員の福利向上を目的とし、全従業員に公平に提供される費用が対象となります。
一方、交際費は取引先との関係強化を目的とした支出であり、社内飲食費でも特定の従業員のみが対象の場合は交際費とみなされることがあります。経費として認められるためには、業務関連性が明確であることが必要です。
実務上の処理では、社内規程を整備し、支出の目的を明確にすることが重要です。
例えば、社員旅行や健康診断費用は福利厚生費として計上可能ですが、特定の従業員のみが対象の場合は給与課税の対象となる可能性があります。
適切な記録を残し、税務調査時の対応をスムーズにすることが求められます。
6-4福利厚生費として認められるための「社会通念上妥当」の判断基準
福利厚生費は、企業が従業員の生活向上を目的として支出する費用ですが、税務上認められるためには「社会通念上妥当」であることが求められます。
これは、支出が一般的な企業活動の範囲内であり、過度に高額でないことを意味します。
例えば、社員旅行や健康診断費用は、全従業員に公平に提供される場合、福利厚生費として認められます。
しかし、特定の従業員のみが対象となる場合や、過度に豪華な内容である場合は、給与課税の対象となる可能性があります。
実務上は、支出の目的や金額を明確にし、社内規程を整備することが重要です。税務調査時に説明できるよう、証憑書類を適切に保管することで、税務リスクを軽減できます。
6-5法定福利費と法定外福利費の分類実務と会計処理の違い
福利厚生費は「法定福利費」と「法定外福利費」に分類されます。
法定福利費は、企業が法律に基づき負担する社会保険料や労働保険料などを指し、全額損金算入が可能です。
一方、法定外福利費は企業が任意で提供する福利厚生(例:住宅手当、社員旅行、健康診断費用)であり、税務上の取り扱いに注意が必要です。
会計処理では、法定福利費は「法定福利費」勘定科目で計上され、法定外福利費は「福利厚生費」として処理されます。
法定外福利費は、全従業員に公平に提供されることが求められ、特定の従業員のみを対象とすると給与課税の対象となる可能性があります。
適切な分類と記帳を行うことで、税務リスクを軽減し、企業の財務管理を適正化できます。
7 福利厚生費の戦略的活用と実務まとめ
福利厚生費を戦略的に活用することで、企業の税務負担を軽減しながら従業員満足度を向上させることが可能です。
カフェテリアプランの導入や健康支援制度の整備など、企業の目的に合った施策を選定し、効果的な運用を行いましょう。
7-1コンプライアンスと効果を両立させる福利厚生費の管理体制
福利厚生費の適正な管理は、企業の信頼性向上と従業員満足度の向上に直結します。コンプライアンスを確保するためには、社内規程の整備が不可欠です。
例えば、支給対象や金額の基準を明確にし、全従業員に公平に提供される仕組みを構築することで、税務リスクを軽減できます。
また、福利厚生費の効果を最大化するには、従業員のニーズを把握し、柔軟な制度設計を行うことが重要です。
選択型福利厚生制度を導入することで、個々のライフスタイルに合った福利厚生を提供でき、満足度向上につながります。
適切な記録管理と定期的な見直しを行い、企業の持続的な成長を支える福利厚生制度を構築しましょう。
7-2人事戦略と税務対策を連動させた福利厚生費活用
福利厚生費を戦略的に活用することで、企業は従業員満足度を向上させながら税務負担を適正化できます。
選択型福利厚生制度(カフェテリアプラン)の導入では、従業員が自身のニーズに合った福利厚生を選択でき、モチベーション向上につながります。
また、社宅制度や健康診断費用を適切に設計することで、税務上のメリットを享受しつつ、従業員の生活支援を強化できます。
福利厚生をうまく活用することで、例えば、社員旅行を福利厚生費として計上し、税務リスクを回避しながら社内の結束力を高めることができます。
さらに、社内規程を整備し、全従業員に公平に提供することで、税務調査時の指摘を防ぐことができます。
これらの福利厚生制度の適切な運用によって、企業の成長と従業員の満足度向上を両立できるのです。










