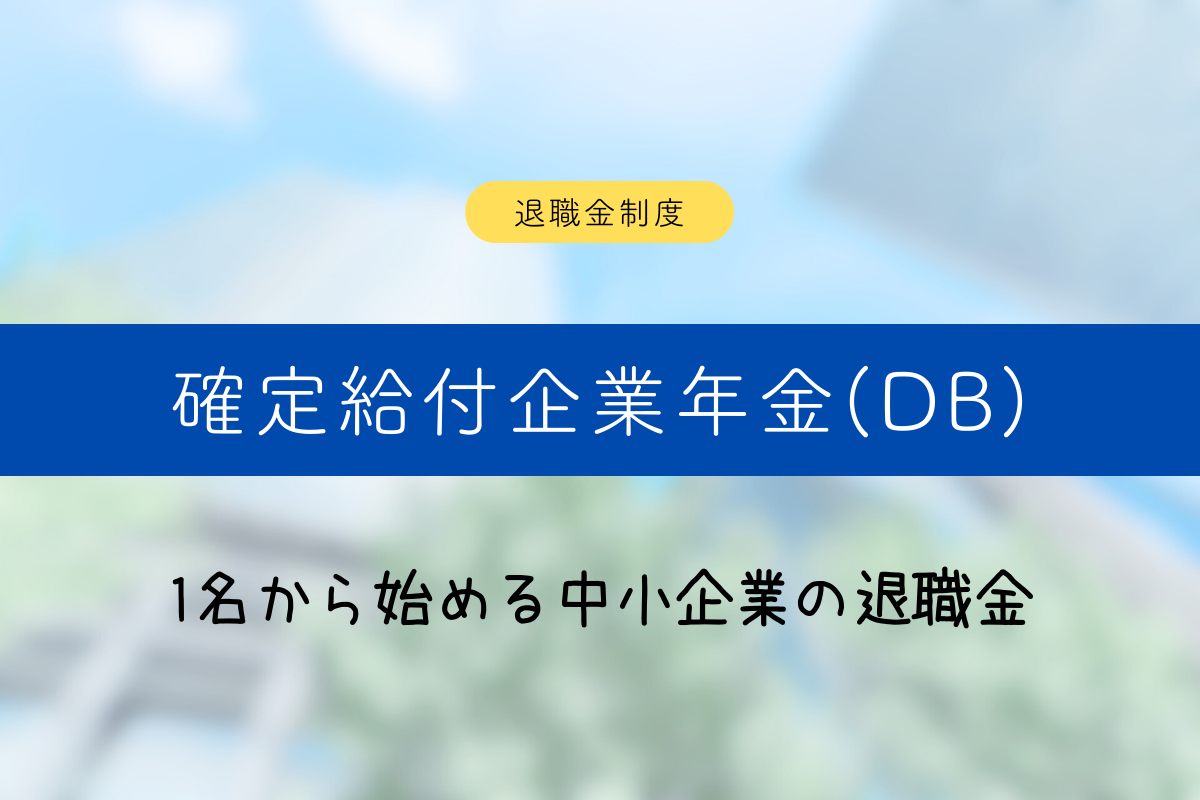人件費の削減方法を考える|給与だけに頼らない人件費最適化戦略
企業における人件費の削減方法は、給与カットだけではありません。
社会保険料(法定福利費)の削減や抑制、採用コスト・離職コストの改善、生産性向上による人件費率改善など、人件費の構造を理解し取り組むことで、従業員の満足度を維持しながら人件費を削減することができます。
本記事では、これらの給与削減に頼らない人件費最適化の具体的な手法と実践方法を詳しく解説します。賃上げが必要とされる状況であっても、従業員の手取り向上と企業の人件費負担軽減を同時に実現するWIN-WINの戦略をお伝えします。
目次
人件費削減で失敗しないために
給与カットのリスク
企業が人件費削減を検討する際、最初に思いつくのが基本給や賞与のカットです。確かに即効性はありますが、この方法には大きなリスクが潜んでいます。
給与カットを実施すると、まず優秀な人材から流出が始まります。市場価値の高い従業員ほど転職先の選択肢が多く、より好条件の企業へ移ってしまうためです。残った従業員のモチベーションも低下し、生産性の著しい低下を招きます。
さらに、採用市場での競争力も失われます。給与水準の低い企業として認知されてしまうと、新規採用が困難になり、結果的に採用コストが増大するという悪循環に陥ることも少なくありません。
特に現在のような人手不足の環境では、給与カットは企業の競争力を決定的に損なう可能性があります。短期的なコスト削減のために、長期的な企業価値を毀損してしまうのです。
人件費削減の優先順位
効果的な人件費削減を実現するためには、適切な優先順位で施策を検討することが重要です。
第1優先:構造的な無駄の削減
最初に着手すべきは、従業員への直接的な影響が少ない部分の最適化です。採用プロセスの効率化、業務改善による生産性向上などが該当します。これらは従業員の給与に手を付けることなく、人件費を削減できる可能性があります。
第2優先:報酬体系の再設計
次に検討すべきは、給与・退職金・福利厚生のバランス最適化です。総額を維持しながら配分を変更することで、社会保険料の削減や税制優遇の活用が可能になります。また、成果連動型報酬への移行や、雇用形態の多様化も選択肢となります。
第3優先:直接的な人件費調整
他の手段を尽くした後の最終手段として、賞与の調整や諸手当の見直しを検討します。基本給の改定は労働契約の根幹に関わるため、本当に最後の選択肢と考えるべきでしょう。
この優先順位に従うことで、従業員への影響を最小限に抑えながら、持続可能な人件費削減を実現できます。
人件費削減のアプローチ方法
人件費削減には、いくつかのアプローチが存在します。それぞれの特徴を理解し、自社に最適な方法を選択することが成功の鍵となります。
| 種類 | 削減対象 | 即効性 | 従業員への影響 | 推奨度 |
|---|---|---|---|---|
| 直接人件費の調整 | 給与・賞与 | 高 | 大きい | △ |
| 法定福利費の最適化 | 社会保険料 | 中 | 小さい | ◎ |
| 採用コストの削減 | 採用・教育費 | 低 | ほぼなし | ◎ |
| 報酬体系の再設計 | 給与構造 | 中 | 中程度 | ○ |
| 雇用形態の最適化 | 人員構成 | 中 | 中程度 | ○ |
| 生産性向上 | 人件費率 | 低 | プラス | ◎ |
各アプローチは単独でも効果がありますが、組み合わせることでより大きな成果を得られます。次章から、それぞれの具体的な内容を詳しく見ていきましょう。
人件費とは|全体構造の理解
人件費削減を考える前に、まず人件費の全体構造を理解することが重要です。
人件費の主要構成要素
人件費は大きく4つのカテゴリーに分類できます。
直接人件費
ここでは、基本給、諸手当、時間外手当、賞与など、従業員に直接支払われる金額(総支給額)を指します。
法定福利費
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料などの会社負担分で、給与支給額の約15%に相当します。40歳以上の従業員については介護保険料も加わります。
法定外福利費
退職金積立、社宅・住宅補助、法定外の健康診断、慶弔見舞金、社員旅行費など、企業が独自に提供する福利厚生にかかる費用です。企業によって0-10%程度と幅があります。
採用・教育関連費
求人広告費、人材紹介手数料、採用活動経費、新人研修費、スキルアップ研修費など、人材の獲得と育成にかかる費用です。
これらを合計すると、実際の人件費は給与支給額の1.3~1.5倍になることが一般的です。この「見えない人件費」を把握することが、効果的な削減の第一歩となります。
業種別・規模別の人件費構造
業種や企業規模によって、人件費構造には大きな違いがあります。自社の特徴を理解することで、より効果的な削減策を選択できます。
業種による特徴
例えば、製造業では、基本給の比重が高く、賞与による調整幅が大きい傾向があります。また、技能手当や現場手当など、業務に直結した手当が多いのも特徴です。
サービス業では、パート・アルバイトの比率が高く、時間外手当の占める割合が大きくなります。繁忙期と閑散期の差が激しい業種では、人件費の変動も大きくなります。
IT業界では、基本給を抑えめにして、成果連動賞与や資格手当の比重を高くする企業が多く見られます。また、教育研修費への投資も他業種より多い傾向があります。
建設業では、現場手当や危険手当など、諸手当の比重が高くなります。また、社会保険加入の徹底が業界全体の課題となっています。
企業規模による特徴
例えば、従業員10人未満の企業では、社会保険の適用除外となるケースもあり、法定福利費率が低い場合があります。一方で、退職金制度がない企業が多く、その分を給与で補っている傾向があります。
10-50人規模では、基本的な法定福利費は負担していますが、退職金制度の導入率は約50%にとどまります。採用は縁故や紹介が中心で、採用コストは比較的低く抑えられています。
50-100人規模になると、各種手当や福利厚生が充実し始め、人件費率が上昇する傾向があります。管理部門の設置により、間接人員の比率も高まります。
100人以上の企業では、管理職比率の上昇により平均給与が高くなる傾向があります。一方で、スケールメリットにより、一人当たりの採用・教育コストは低減できる場合もあります。
人件費が高くなる原因
様々な事情により、人件費が割高になってしまうケースがあります。その原因を理解することで、改善のポイントが見えてきます。
給与偏重の報酬体系
退職金制度がない企業では、従業員の処遇改善や賃上げ要請に応える際、給与のみで調整せざるを得ません。
しかし、例えば給与を1万円上げると、社会保険料の会社負担が約1,500円増加し、従業員の手取りも税金と社会保険料で約3,000円目減りします。つまり、会社は11,500円のコストをかけても、従業員の手取りは7,000円しか増えないという非効率な構造になっているのです。
このような給与一辺倒の報酬改善は、企業にとっても従業員にとっても最適とは言えません。同じコストをかけるなら、より効果的な配分方法があるはずです。
採用コストの増大
知名度の低い企業では、採用に苦戦することも多く、人材紹介会社に頼るケースがあります。その場合、年収の30-35%という高額な手数料を支払うことも珍しくありません。
さらに、せっかく採用した人材が短期間で離職してしまうと、採用コストが無駄になるだけでなく、再度採用活動を行う必要が生じます。この悪循環が、採用関連費を押し上げる要因となっています。
非効率な人員配置
業務が属人化している企業では、特定の従業員が休むと業務が停滞してしまうため、余剰人員を抱えることに繋がります。また、繁忙期と閑散期の差が大きい業種では、ピーク時に合わせた人員配置となり、閑散期に余剰が発生します。
多能工化やクロストレーニングが進んでいない企業では、このような非効率が常態化してしまいます。
生産性の低さ
IT投資の遅れや業務プロセスの非効率により、一人当たりの生産性が低くなってしまっている企業も多く存在します。同じ売上を上げるのに、より多くの人員を必要とするため、非効率です。
これらの原因は相互に関連しており、一つを改善することで他の問題も解決に向かうことがあります。では、具体的な削減方法を見ていきましょう。
直接人件費の削減|給与・賞与を下げる方法
基本給と手当の見直しによる人件費削減
大前提として、直接的な給与調整は最終手段と位置付けるべきですが、実施する場合は戦略的なアプローチが必要です。
基本給より諸手当から見直す
基本給は労働契約の根幹であり、一度設定すると引き下げが非常に困難です。労働条件の不利益変更には厳格な要件があり、従業員の同意なく基本給を下げることは原則としてできません。また、基本給は残業代や賞与の計算基礎となるため、その調整は広範な影響を及ぼします。
一方、諸手当は比較的柔軟に見直しが可能です。支給基準を明確化し、真に必要な場合のみ支給するよう改めることで、合理的な削減が可能となります。例えば、家族手当や住宅手当などの属人的手当を、職務に応じた手当に再編することも選択肢の一つです。
また、複数の類似した手当を統合することで、管理コストの削減も図れます。細分化された手当体系は、管理が煩雑になるだけでなく、従業員にとっても分かりにくいものとなりがちです。
賞与を調整する
賞与は企業業績に連動させやすく、従業員の理解も得やすい調整項目です。固定的な賞与から業績連動型への移行は、企業の支払い能力に応じた柔軟な人件費管理を可能にします。
ただし、賞与の大幅な削減は、採用市場での競争力に影響します。同業他社の支給水準を意識しながら、慎重に検討する必要があるでしょう。また、個人の成果と連動させることで、優秀な人材のモチベーション維持も図れます。
賃金体系の変更による人件費削減
年功序列型から職務・成果主義型への転換により、人件費の効率的な配分を目指します。
職務給・役割給の導入・見直し
職務給制度では、年齢や勤続年数ではなく、担当する職務の価値に応じて給与を決定します。これにより、同一労働同一賃金の実現とともに、人件費と生産性の連動性を高められます。
役割給は、組織における役割と責任の大きさに応じた給与体系です。管理職と専門職でキャリアパスを分けることで、マネジメントを望まない優秀な技術者にも適切な処遇を可能とします。
評価制度との連動
賃金体系の変更には、公正で透明性の高い評価制度が不可欠です。評価基準を明確にし、評価結果と昇給・賞与を連動させることで、従業員の納得性を高めます。
ただし、評価制度の設計と運用には注意が必要です。過度に複雑な制度は、評価にかかる時間とコストを増大させ、かえって非効率となる場合があります。
雇用形態の細分化による人件費削減
多様な雇用形態を組み合わせることで、業務特性に応じた最適な人件費構造を実現できます。
正社員の区分を細分化
業務内容や勤務条件に応じた社員区分を設けることで、人件費の効率化が可能です。
例えば、勤務地限定正社員(エリア社員)制度により、転勤がない分、給与水準を調整できます。職務限定正社員は、特定の業務に特化することで、専門性を高めながら人件費をコントロールできます。時間限定正社員は、育児や介護との両立を支援しながら、フルタイム換算での人件費を抑制できます。
このような限定正社員制度は、従業員のワークライフバランスと企業の人件費管理を両立させる有効な手段となります。
柔軟な雇用形態の組み合わせ
コア業務は無限定正社員、定型業務は職務限定正社員、地域密着業務はエリア限定正社員といったように、業務特性に応じた最適な雇用形態を選択します。
また、パート・アルバイトについても、社会保険適用拡大(従業員51人以上の企業で週20時間以上勤務が対象)を踏まえ、短時間正社員への転換や、業務委託への切り替えなど、戦略的な対応が求められます。
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」
給与以外の人件費削減|法定福利費、福利厚生費、採用費等の削減
法定福利費(社会保険料)の削減方法
法定福利費は給与に約15%かかることになる大きな項目です。厚生年金法等に基づき算出されるため、自由にコントロールできる費用ではありませんが、多くの企業がその削減可能性を見落としています。
社会保険料の仕組みを理解する
社会保険料は「標準報酬月額」を基準に計算されます。この標準報酬月額には、基本給だけでなく、諸手当や残業代、通勤手当なども含まれます。つまり、現金で支給するものは原則すべて社会保険料の対象となるのです。
しかし、すべての報酬が社会保険料の対象となるわけではありません。現物給付や一定の要件を満たす福利厚生は、社会保険料の算定から除外される場合があります。
社会保険料の算定から除外される報酬
標準報酬月額に含まれない報酬を活用することにより、社会保険料を抑制することができます。以下のような報酬は、一定の要件を満たせば社会保険料の算定対象から除外されます。
社宅・住宅関連
住宅手当を現金で支給すると全額が標準報酬月額に含まれますが、会社が借り上げた社宅を提供する場合、従業員から徴収する家賃と実際の家賃との差額は標準報酬月額に含まれません。例えば、家賃10万円の物件を会社が借り上げ、従業員から3万円を徴収する場合、7万円分は社会保険料の対象外となります。
食事補助
現物での食事提供は、従業員が食事代の50%以上を負担し、かつ会社負担が月額3,500円(税抜)以下であれば、標準報酬月額に含まれません。社員食堂での食事提供や、弁当の現物支給がこれに該当します。
その他の現物給付
制服の貸与、業務に必要な作業用品の支給、社内託児所の利用なども、一定の要件を満たせば標準報酬月額から除外されます。また、出張旅費や宿泊費の実費精算分も、業務上必要なものであれば算定対象外です。
これらを戦略的に活用することで、従業員の実質的な処遇を改善しながら、労使双方の社会保険料負担を軽減できます。
採用コスト・離職コストの削減手法
採用関連費は見えにくいコストですが、離職率の高い企業では人件費全体の10-20%に達することもあります。
真の採用コストを把握する
採用コストは求人広告費や人材紹介手数料だけではありません。説明会や面接にかかる人件費、適性検査や健康診断の費用、内定者フォローの費用なども含まれます。
さらに重要なのが、離職に伴う隠れたコストです。引き継ぎ期間中の生産性低下、新人が戦力化するまでの教育コスト、既存社員の負担増によるモラール低下など、数値化しにくいコストも無視できません。
定着率向上が最大のコスト削減
採用コストを削減する最も効果的な方法は、離職を防ぐことです。そのためには、従業員が長く働きたいと思える環境づくりが重要となります。
退職金制度の導入は、長期勤続へのインセンティブとなります。将来の生活に対する安心感を提供することで、従業員の定着率向上が期待できます。
キャリア開発支援も重要です。スキルアップの機会を提供し、明確なキャリアパスを示すことで、従業員の成長意欲を満たすことができます。
職場環境の改善も欠かせません。ワークライフバランスの推進や、社内コミュニケーションの活性化により、働きやすい職場づくりを進めることが、結果的に採用コストの削減につながります。
生産性向上による人件費率の改善
人件費の絶対額を削減するのではなく、売上高に対する人件費率を改善するアプローチも重要です。
業務効率化は、IT化・デジタル化から始めるのが効果的です。定型業務の自動化、ペーパーレス化、クラウドツールの活用などにより、作業時間を大幅に削減できます。
業務プロセスの見直しも重要です。無駄な会議や報告書を削減し、意思決定のスピードを上げることで、組織全体の生産性が向上します。
従業員のスキルアップも生産性向上に直結します。研修や資格取得支援により、一人ひとりの能力を高めることで、少ない人数でより多くの成果を上げられるようになります。
また、商品・サービスの高付加価値化により、売上単価を向上させることも重要です。価格競争から脱却し、独自の価値を提供することで、人件費率の改善が可能となります。
退職金制度を活用した人件費の最適化
人件費配分における退職金制度の位置づけ
前述の通り、給与偏重の報酬体系は労使双方にとって非効率です。この構造的問題を解決するには、報酬を「給与」「退職金」「福利厚生」の3要素でバランスよく配分することが重要です。
理想的な報酬配分とは
効率的な人件費管理では、それぞれの要素を以下のように位置付けます。
- 給与:日常生活に必要な安定収入
- 退職金:将来の生活保障と長期勤続インセンティブ
- 福利厚生:現在の生活の質向上
この配分により、同じ人件費総額でも従業員の実質的な受取額を最大化できます。特に退職金は、退職所得控除(勤続20年で800万円、30年で1,500万円の非課税枠)という大きな税制優遇があり、給与で支払うより遥かに効率的です。
退職金制度導入のメリット
退職金制度は大企業だけのものと思われがちですが、中小企業にも大きなメリットがあります。
企業側のメリット
人材の定着率向上は、最大のメリットです。退職金制度があることで、従業員に長期勤続のインセンティブを与えられます。これにより、採用コストの削減と組織の安定化が図れます。
税務上の優遇も見逃せません。適切に設計された退職金積立は、全額損金算入が可能です。また、計画的な資金準備により、退職時の大きな支出にも対応できます。
採用市場での競争力向上も期待できます。求職者にとって、退職金制度の有無は重要な判断基準の一つです。特に、同業他社との差別化要因として機能します。
従業員側のメリット
税制上の優遇は、従業員にとって大きなメリットです。退職所得控除により、勤続20年で800万円、30年で1,500万円までが非課税となります。また、控除額を超える部分も、その2分の1のみが課税対象となるため、大幅な節税効果があります。
将来への安心感も重要です。公的年金だけでは老後の生活に不安を感じる中、企業の退職金制度は重要な老後資金となります。計画的な資産形成が可能となり、ライフプランを立てやすくなります。
選択制退職金制度という選択肢
退職金制度のもたらすメリットは前述のとおりですが、新たに退職金制度を導入するには追加原資が必要となり、多くの企業にとってハードルが高いのも事実です。
この課題を解決するのが「選択制退職金制度」です。
選択制退職金制度の仕組み
選択制退職金制度では、従業員が自らの意思で、給与の一部を退職金積立に充てることができます。例えば、月給30万円の従業員が、そのうち2万円を退職金積立に回すことを選択すると、月給は28万円となり、2万円が退職金として積み立てられます。
この積立分は社会保険料の算定対象から除外されるため、標準報酬月額が下がり、労使双方の社会保険料負担が軽減されます。退職時には、積み立てた退職金に退職所得控除が適用され、税制上のメリットも享受できます。
選択制のメリット
企業にとっては、新たな原資を必要とせずに退職金制度を導入できる点が最大のメリットです。また、社会保険料の会社負担分も軽減されます。
従業員にとっては、自分のライフスタイルやニーズに応じて、現在の手取りを重視するか、将来の資産形成を重視するかを選択できます。若い世代は手取りを重視し、中高年は退職金積立を増やすといった柔軟な対応が可能です。
導入にあたっての注意点
選択制退職金制度には、確定給付企業年金(DB)型、確定拠出年金(DC)型などがあります。例えば「YUKINつみたてDBプラン」のような総合型の確定給付企業年金は、1名から導入可能で、中小企業でも始めやすい制度です。
ただし、導入にあたっては従業員への十分な説明が不可欠です。社会保険料の減少により、将来受け取る年金額が減少する可能性もあるため、メリットとデメリットを正確に伝える必要があります。また、労使間での合意形成も重要なプロセスとなります。
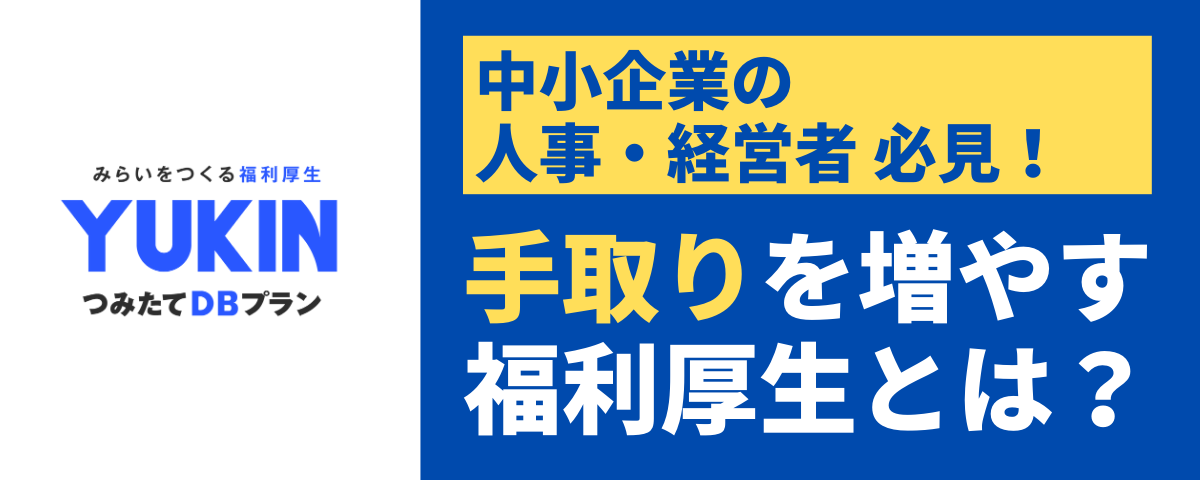
YUKINつみたてDBプラン
選択制退職金制度で従業員の資産形成を柔軟にサポート。企業の負担を抑えながら、従業員一人一人が自分に合った資産形成を選択できる制度です。
人件費削減におけるポイント
賃上げと人件費削減の両立
政府や経済界から継続的な賃上げ要請がある中、単純な人件費削減は企業イメージを損なうリスクがあります。
そのため、実質手取りの向上を図り、額面上の賃上げ以上の効果を追求することが重要となります。
選択制退職金制度などを活用し、社会保険料負担を軽減することで、従業員の手取り額を増やすことが可能です。生涯賃金で見れば、退職所得控除の活用により、さらに大きなメリットが生まれます。
生産性向上による原資確保も重要です。売上の増加や業務効率化により、賃上げ原資を創出できれば、人件費率を維持しながら賃上げが可能となります。
また、メリハリのある配分により、限られた原資を効果的に活用できます。一律の賃上げではなく、成果を上げた従業員に重点的に配分することで、組織全体のモチベーション向上につながります。
人材確保と人件費削減の両立
深刻な人手不足の中、人材確保と人件費削減を両立させることは、企業にとって大きな課題です。
採用費削減のためには、定着率向上が根本的かつ最も効果的なアプローチです。退職金制度や福利厚生の充実により、従業員の定着率を高めることで、採用頻度を減らし、結果的に採用コストを削減できます。
多様な人材活用も重要です。子育て中の優秀者な人材の獲得、シニア人材の豊富な経験と安定した勤務の獲得、外国人材の新たな視点を獲得することにより、組織の多様性向上にも貢献します。
テレワークの導入により地方の優秀な人材を活用したり、副業・兼業を認めることで、専門性の高い人材を柔軟に活用することも検討しましょう。
社会保険適用拡大への対策
現在、従業員51人以上の企業ではパート従業員への社会保険適用が義務付けられています。
単純に勤務時間を週20時間未満に調整することは、人手不足の中では現実的ではありません。むしろ、この機会を活用して、雇用形態の最適化を図るべきでしょう。
優秀なパート従業員を正社員に転換することで、戦力の安定化が図れます。また、業務の見直しにより、効率化を進めるきっかけにもなります。
重要なのは、従業員の希望も踏まえた対応です。社会保険加入を望む従業員と、扶養の範囲内で働きたい従業員、それぞれのニーズに応じた働き方を提供することが、人材確保にもつながります。
まとめ:企業の持続可能な人件費削減
短期・中期・長期の視点で考える
この記事で解説した人件費削減のアプローチは、それぞれ異なる特徴を持ち、企業の状況に応じて使い分ける必要があります。
短期的には、賞与の業績連動化や諸手当の見直しなど、比較的実施しやすい施策から着手します。これらは即効性がありますが、従業員への影響も考慮して慎重に進める必要があります。
中期的には、選択制退職金制度の導入や採用プロセスの改善など、構造的な改革に取り組みます。これらは導入に時間がかかりますが、持続的な効果が期待できます。
長期的には、生産性向上投資や賃金体系の抜本改革など、企業の競争力強化につながる施策を実施します。これらは時間と投資が必要ですが、企業価値の向上にも寄与します。
人件費削減から人的資本経営へ
人件費削減の最終目標は、単なるコストカットではありません。限られた経営資源を最適に配分し、従業員と企業がともに成長する仕組みづくりこそが重要です。
特に注目すべきは、給与偏重の報酬体系を見直し、給与・退職金・福利厚生のバランスを最適化することです。選択制退職金制度のような新しい仕組みを活用すれば、追加原資なしに従業員の実質的な処遇改善と企業の人件費最適化を両立できます。
人手不足が深刻化し、賃上げ要請が続く現在、従来型の人件費削減は限界を迎えています。これからは、従業員満足度を高めながら、構造的に人件費を最適化する戦略が求められます。
企業にとって人件費管理は永遠の課題ですが、正しい知識と戦略を持つことで、必ず解決の道は開けます。本記事で紹介した手法を参考に、自社に最適な人件費削減戦略を構築してください。
従業員と企業が Win-Win の関係を築くことができれば、それは単なるコスト削減を超えて、企業の持続的成長の基盤となるはずです。
よくあるご質問
人件費削減は給与カット以外に方法はありますか?
むしろ給与カット以外の方法から検討すべきです。
法定福利費(社会保険料)の最適化、採用コストの削減、生産性向上による人件費率の改善など、従業員への直接的な影響が少ない方法が複数存在します。
特に選択制退職金制度を活用すれば、従業員の手取りを増やしながら会社の社会保険料負担を軽減できる可能性もあります。社会保険料を削減する方法はありますか?
社宅制度の活用、食事補助の現物支給などにより、社会保険料を抑制できます。
また、選択制退職金制度では、従業員が給与の一部を退職金積立とするため、標準報酬月額が下がり、労使双方の社会保険料負担を軽減できる可能性があります。
ただし、社会保障給付減少のデメリットも発生するため、適切な制度設計と従業員への説明が不可欠です。従業員10名程度の小規模企業でも実施できる人件費削減方法は?
小規模企業は、大企業に比べ必然と削減額は小さくなるものの、様々な変化に柔軟に対応できるメリットがあります。
選択制退職金制度なら1名から導入可能ですし、採用を縁故・紹介中心にすることで採用コストを大幅に削減できます。また、多能工化を進めやすく、業務の属人化を防ぐことで効率的な人員配置が可能です。退職金制度がない企業が多いと聞きますが、導入すべきでしょうか?
中小企業の約30%は退職金制度がありませんが、導入のメリットは大きいです。
人材の定着率向上、採用競争力の強化、税制優遇の活用などが期待できます。特に選択制退職金制度なら、新たな原資を必要とせずに導入でき、従業員も自分のニーズに応じて選択できるため、導入のハードルが低くなります。社会保険適用拡大の影響と対策は?
従業員51人以上の企業で、週20時間以上勤務するパート従業員が社会保険加入対象となります。
単純に勤務時間を削減するのではなく、この機会に雇用形態の最適化を図るべきです。優秀なパート従業員の正社員化や、業務効率化による総労働時間の削減など、前向きな対応が重要です。賃上げ要請がある中で人件費削減は可能ですか?
賃上げを行えば、当然ながら人件費は増加してしまいますが、その増加額を抑制、効率化することは可能です。
賃上げは従業員の給与だけではなく、社会保険料等も増加します。
重要なのは「給与の額面」のみではなく、「実質的な処遇」です。退職金や福利厚生などを組み合わせてみましょう。人件費削減で従業員のモチベーションが下がらないか心配です。
確かにその懸念は重要です。
だからこそ、給与カットのような直接的な削減は最終手段とし、まずは構造的な改善から着手すべきです。
法定福利費や採用コストの削減は、従業員への影響がほとんどありません。
むしろ、退職金制度の導入や生産性向上投資は、従業員のモチベーション向上につながります。業績連動型賞与への移行は従業員に受け入れられますか?
透明性の高い評価基準と丁寧な説明があれば、多くの場合受け入れられます。
固定賞与から業績連動への移行は、会社の業績が従業員の努力で改善できることを実感できる仕組みでもあります。
ただし、生活給に相当する部分は月給で安定的に支給し、賞与は本当の意味での「ボーナス」として位置付けることが重要です。離職率が高い業界ですが、採用コスト削減は可能ですか?
離職率が高い業界こそ、採用コスト削減の余地が大きいです。
まず離職の原因を分析し、退職金制度の導入、キャリアパスの明確化、職場環境の改善など、定着率向上の施策を実施します。
採用手法も、人材紹介依存から、リファラル採用や直接採用を見直すことで、大幅なコスト削減に繋がる可能性があります。選択制退職金制度のデメリットはありますか?
あります。注意すべきは、社会保険料が減ることで社会保障給付が減少する可能性があります。
そのため、従業員への十分な説明と理解が不可欠です。
ただし、退職所得控除の活用により生涯賃金では有利になるケースが多く、メリットとデメリットを正確に理解した上で選択できる制度設計が求められます。