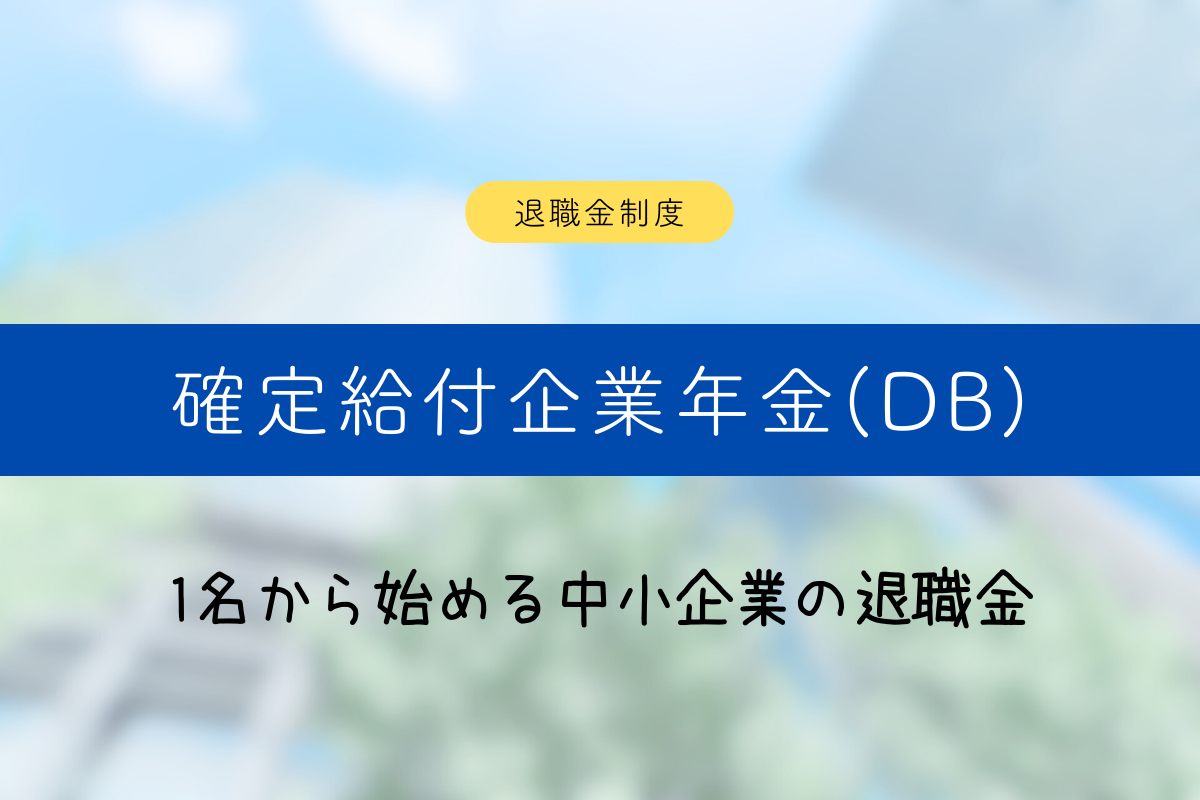退職金制度の作り方|中小企業向け相場・計算・設計手順
退職金制度を導入することが決まったら、次に重要なのは「具体的な制度設計」です。どのような計算方法を選ぶかで、従業員のモチベーションや企業の負担額、制度の運用しやすさが大きく変わります。
本記事では、中小企業が退職金制度を実際に設計する際の4つの計算方法について、具体的な設計例から運用時の注意点まで詳しく解説します。自社に最適な退職金制度の設計にお役立てください。
目次
基本給連動型|最も一般的で分かりやすい計算方式
基本給連動型は「基本給×勤続年数×支給率×退職事由係数」で計算する最もポピュラーな方式です。従業員にとって分かりやすく、長期勤続へのインセンティブを設計しやすいのが特徴です。
基本的な計算式と設計例
計算式
退職金 = 退職時の基本給 × 勤続年数別支給率 × 退職事由係数
支給率テーブルの設計例
| 勤続年数 | 支給率 | 累積支給月数 | 退職事由係数 |
|---|---|---|---|
| 1~3年 | 0.3ヶ月/年 | 0.9ヶ月 | 自己都合:0.6、会社都合:1.0 |
| 4~5年 | 0.5ヶ月/年 | 1.9ヶ月 | 自己都合:0.8、会社都合:1.0 |
| 6~10年 | 1.0ヶ月/年 | 6.9ヶ月 | 自己都合:0.9、会社都合:1.0 |
| 11~15年 | 1.2ヶ月/年 | 12.9ヶ月 | 自己都合:1.0、会社都合:1.0 |
| 16~20年 | 1.5ヶ月/年 | 18.9ヶ月 | 自己都合:1.0、会社都合:1.0 |
| 21年~ | 2.0ヶ月/年 | – | 自己都合:1.0、会社都合:1.0 |
計算例 基本給25万円、勤続12年、自己都合退職の場合:
- 1~3年:0.3×3年=0.9ヶ月
- 4~5年:0.5×2年=1.0ヶ月
- 6~12年:1.2×7年=8.4ヶ月
- 合計:10.3ヶ月×25万円×1.0(自己都合係数)=257.5万円
設計時の重要ポイント
1. 支給率テーブルの設計戦略
- 早期離職抑制:3~5年の支給率を低めに設定し、係数でさらに減額
- 中堅社員の定着:6~15年の支給率を段階的に上昇
- 長期勤続奨励:20年超で大幅な支給率アップ
2. 基本給の定義を明確化
- 諸手当を含むか除くかで退職金額が大きく変動
- 一般的には「基本給のみ」または「基本給+職務手当」
- 将来の昇給を考慮した財務シミュレーションが必要
3. 運用時の注意点
- 基本給変動リスク:昇給により退職金コストが予想以上に増加する可能性
- 勤続年数の端数処理:1年未満は切り捨て、月割り計算など明確化
- 定年延長時の対応:60歳以降の勤続年数をどう扱うか事前決定
定額制退職金|コスト予測しやすいシンプル設計
定額制は勤続年数に応じて一律の金額を支給する方式。将来のコスト予測が立てやすく、従業員にとっても退職金の見通しが明確な制度です。
基本的な計算式と設計例
計算式
退職金 = 勤続年数に応じた定額 × 退職事由係数
定額テーブルの詳細設計例
| 勤続年数 | 基準額 | 自己都合係数 | 会社都合係数 | 実支給額(自己都合) |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3万円 | 0.5 | 1.0 | 1.5万円 |
| 3年 | 15万円 | 0.6 | 1.0 | 9万円 |
| 5年 | 30万円 | 0.8 | 1.0 | 24万円 |
| 10年 | 80万円 | 0.9 | 1.0 | 72万円 |
| 15年 | 150万円 | 1.0 | 1.0 | 150万円 |
| 20年 | 250万円 | 1.0 | 1.0 | 250万円 |
| 25年 | 400万円 | 1.0 | 1.0 | 400万円 |
| 30年 | 600万円 | 1.0 | 1.0 | 600万円 |
設計時の重要ポイント
1. 定額テーブルの設定戦略
- 業界相場との比較:同業他社の退職金水準を調査
- 段階的な増額設計:10年、15年、20年で大きくステップアップ
- 財務負担の平準化:年間の退職金総額を予算内に収める設計
2. インフレ対応の仕組み
- 定期見直し条項:3~5年ごとの金額見直し規定
- 物価連動方式:消費者物価指数との連動も選択肢
- 業績連動調整:会社の業績に応じた調整機能
3. 運用時の注意点
- コスト固定化の利点:人件費予算の立てやすさ
- 個人差の解消:給与格差に関わらず公平な制度
- モチベーション設計:勤続年数以外の要素を別制度で補完
ポイント制退職金|成果と貢献度を反映する柔軟な仕組み
ポイント制は勤続年数や役職・等級、個人の業績評価を「ポイント」として数値化し、累積ポイントで退職金を算出する最も柔軟な制度です。
基本的な計算式と設計例
計算式
退職金 = 累計付与ポイント × ポイント単価 × 退職事由係数
ポイント付与の詳細設計例
| 要素 | 区分 | 年間付与ポイント | 備考 |
|---|---|---|---|
| 基本ポイント | 勤続 | 20ポイント/年 | 全員に付与 |
| 役職ポイント | 主任 | +5ポイント/年 | 役職在任中のみ |
| 係長 | +10ポイント/年 | ||
| 課長 | +15ポイント/年 | ||
| 部長 | +25ポイント/年 | ||
| 評価ポイント | S評価 | +8ポイント | 年1回の人事評価 |
| A評価 | +4ポイント | ||
| B評価 | +0ポイント | ||
| C評価 | -2ポイント | ||
| 特別貢献 | 新規事業成功 | +50ポイント | 一時的付与 |
| 資格取得 | +10ポイント | 指定資格のみ |
ポイント単価設定例
- 1ポイント=2,000円(調整により全体コストをコントロール)
計算例 勤続10年、課長3年、平均A評価の場合:
- 基本ポイント:20×10年=200ポイント
- 役職ポイント:15×3年=45ポイント
- 評価ポイント:4×10年=40ポイント
- 合計:285ポイント×2,000円×1.0(退職事由係数)=57万円
設計時の重要ポイント
1. ポイント設計の戦略
- 基本ポイント重視:勤続年数を基本とし、その他は加算方式
- 評価連動の範囲:評価ポイントの影響度を適正レベルに設定
- マイナスポイント:C評価や懲戒処分時の減算ルール
2. ポイント単価の調整機能
- 全体コスト管理:単価変更により退職金総額をコントロール
- 段階的単価:累積ポイント数に応じた単価設定も可能
- 業績連動単価:会社業績に応じた単価調整機能
3. 運用時の注意点
- 評価制度との整合性:人事評価制度の精度が退職金に直結
- ポイント履歴の管理:長期間のポイント記録を正確に保持
- 従業員への情報開示:ポイント残高の定期的な通知が必要
選択制退職金|従業員の多様なニーズに応える新しい設計
選択制退職金は、従業員が「給与として今受け取るか」「将来の退職金として積み立てるか」を選択できる制度です。企業の新たな負担を抑えつつ、従業員の多様なライフプランに対応できる注目の制度として、多くの中小企業で導入が進んでいます。
選択制退職金の基本概要とメリット
例えば月給30万円の従業員が、「給与25万円+退職金積立5万円」を選択すれば、手取りは減りますが将来の退職金が積み立てられ、税制優遇や社会保険料軽減のメリットも受けられます。従業員は定期的に、自分のライフプランに応じて選択内容を変更できます。
主なメリット
- 企業側:新たな負担なしで退職金制度を導入、社会保険料の軽減効果、従業員満足度向上
- 従業員側:ライフプランに応じた柔軟な選択、税制優遇、手取りの実質増加の可能性
注意点 掛金の選択により標準報酬月額が下がる場合、社会保険料負担が軽減する一方で、将来の厚生年金額や傷病手当金等の社会保障給付も減少することになります。従業員には退職金積立のメリットとともに、この点についても丁寧な説明を行い、十分に理解してもらった上で選択してもらうことが重要です。
選択制DCと選択制DBの違い
選択制退職金制度には、「選択制DC(確定拠出年金)」と「選択制DB(確定給付企業年金)」の2つのタイプがあります。
| 項目 | 選択制DC | 選択制DB |
|---|---|---|
| 受取額の確定性 | 運用成果により変動 | あらかじめ給付額が確定 |
| 運用責任 | 従業員が負う | 企業・基金が負う |
| 運用方法 | 従業員が投資信託等から選択 | 基金にて定める |
| 元本保証 | なし(元本割れリスク) | あり(元本+利息保証) |
| 投資知識 | 必要 | 不要 |
| 掛金限度額 | 月額55,000円 | 給与の20%以内(制度により異なる) |
| 社会保険料負担軽減 | あり | あり |
| 税制優遇 | あり | あり |
| 受け取り時期 | 原則60歳まで引き出し不可 | 退職時・休職時に受取可能 |
どちらを選ぶべきか
- 選択制DC:従業員の金融リテラシーが高く、積極的な資産運用を望む場合
- 選択制DB:確実な老後資金を求め、シンプルで分かりやすい制度を望む場合
YUKINつみたてDBプラン|中小企業に最適な選択制DB
選択制DB制度の中でも、「YUKINつみたてDBプラン」は中小企業に特化して設計された制度として注目されています。
YUKINの特徴
- 1名から導入可能:小規模企業でも始めやすい
- 役員・経営者も加入OK:70歳未満まで加入可能
- 柔軟な拠出設定:月1,000円~30万円(給与の20%以内)
- 確定給付型の安心感:元本保証+利息で将来の受取額が明確
- 包括的なサポート:制度設計から運用まで専門スタッフが全面支援
まとめ:自社に最適な退職金制度設計を
4つの計算方法にはそれぞれ特徴があり、企業の規模、業種、企業文化によって最適な選択は異なります。
選択の指針
- 基本給連動型:従来型の安定した制度を求める企業
- 定額制:コスト管理を重視し、シンプルな制度を望む企業
- ポイント制:成果主義で柔軟な制度設計を行いたい企業
- 選択制:従業員の多様性を重視し、新たな負担を抑えたい企業
中小企業には、従業員1名から始められ、会社の新たな負担を抑えながら導入できる「選択制退職金制度(YUKIN)」が特におすすめです。
制度設計から運用までしっかりとイメージし、従業員と企業双方にメリットのある退職金制度を構築していきましょう。
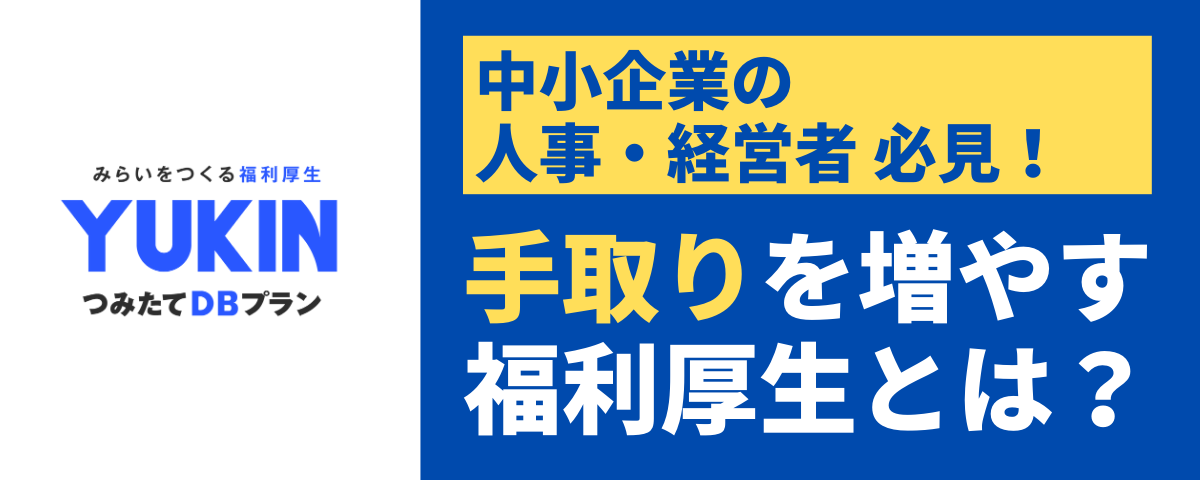
YUKINつみたてDBプラン
選択制退職金制度で従業員の資産形成を柔軟にサポート。企業の負担を抑えながら、従業員一人一人が自分に合った資産形成を選択できる制度です。