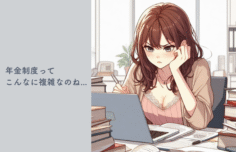【第11回】確定給付企業年金(DB)とは?積立不足・予定利率・運用リスクを徹底解説
確定給付企業年金(DB)は、将来の給付額があらかじめ約束された企業年金制度です。
企業型確定拠出年金(DC)とは異なり、運用リスクは企業が負担し、従業員は投資知識がなくても安定した給付を受けられます。
しかし、予定利率の設定、積立不足への対応、財政検証など、企業側には高度な制度運営が求められます。
本記事では、規約型・基金型の違いから、キャッシュバランスプラン、リスク対応掛金まで、DB制度の仕組みと実務を詳しく解説します。
目次
企業型DCの現実を受けて、DBの仕組みを本格的に学ぶ
企業型DCについて詳しく調べた結果、制度自体は優れているけれど、現実的には多くの課題があることがわかりました。特に従業員の約24%が元本確保型のみで運用している実態や、投資への無関心という構造的な問題。
「制度は良いけど、活用するには相当な投資知識と関心が必要…でも現実は『ほったらかし』が多いんだよね」
そんなことを考えていたとき、サキ先輩から声をかけられました。
「ユキちゃん、DCについて調べてたでしょ?どうだった?」
休憩室でコーヒーを飲みながら、企業型DCについて調べて分かったことを話しました。
「なるほど、やっぱりDCは従業員の投資リテラシーに左右されるのよね。だからこそ、DBという選択肢も重要になってくるの」
「DBですか?確定給付企業年金のことですよね」
「そう。DCとは正反対のアプローチで、従業員は投資の知識がなくても、決まった金額がもらえる仕組みよ。でも企業側から見ると、運用リスクを負うことになるから、制度設計がすごく重要なの」
「詳しく教えてください!DCとの違いも含めて、DBの実態を知りたいです」
サキ先輩は嬉しそうに頷きました。
「いいわね。DBは本当に奥が深い制度だから、時間をかけてじっくり説明するわ」
DB制度の基本構造と加入状況|なぜ最も普及しているのか
確定給付企業年金の規模と位置づけ
サキ先輩に詳しく教えてもらいながら、まずDBの全体像を把握してみました。
確定給付企業年金の現状(2024年3月末)
- 制度数:11,794件
- 加入者数:約903万人
- 資産規模:約70兆円
「903万人!企業型DCの830万人より多いんですね」
「そうなの。特に大企業では、長い歴史のあるしっかりした制度が整備されてることが多いの。でも最近は少し減少傾向にあるのも事実よ」
DBが普及している理由
DBの基本的な魅力
- 従業員の安心感:将来の給付額が確定している
- 投資知識不要:運用は企業・基金が責任を持つ
- 受給権保護:外部積立により倒産リスクから保護
- 税制優遇:拠出時損金算入、受給時退職所得控除等
「従業員からすると、『お任せ』で安心できるってことですね」
「その通り。でも企業から見ると、その『お任せ』の責任がすごく重いのよ」
規約型と基金型の違い|導入要件・運営体制・メリット比較
2つの実施形態の詳細比較
DBには「規約型」と「基金型」の2種類があることは知っていましたが、実務的な違いを詳しく教えてもらいました。
規約型 vs 基金型の詳細比較
| 項目 | 規約型DB | 基金型DB |
|---|---|---|
| 設立要件 | 人数制限なし | 原則300人以上 |
| 設立主体 | 企業 | 企業年金基金(法人) |
| 厚労省手続き | 規約承認 | 基金設立認可 |
| 運営主体 | 企業+受託機関 | 企業年金基金 |
| 代議員会 | 設置不要 | 設置必須(労使同数) |
| 理事会 | 設置不要 | 設置必須 |
| 独立性 | 低い | 高い(法人格) |
| 事務負担 | 企業が直接負担 | 基金が中心 |
| 制度変更 | 企業判断+労使合意 | 代議員会決議 |
「基金型の方が独立性が高いんですね。代議員会って何ですか?」
「代議員会は労使同数で構成される意思決定機関よ。給付設計の変更とか、資産運用方針とか、重要事項を決める場所なの。企業の都合だけでは決められないから、従業員の権利がより保護されるのよ」
複数事業主型という選択肢
「基金型は300人以上が原則だから、中小企業には関係ないのかと思ってたんですが…」
「実は『複数事業主型』っていう仕組みがあるの。複数の企業が共同で一つの基金を設立する方法よ」
複数事業主型基金のメリット
- ・小規模企業でも基金型DBに参加可能
- ・運用の専門性:大規模運用によるスケールメリット
- ・事務負担軽減:基金が制度運営を代行
- ・コスト削減:共通費用による単価削減効果
「なるほど、みんなで一緒にやれば、個別では難しい専門的な運用もできるってことですね」
「そうそう。最近は総合型DB基金で、選択制を導入できるところも出てきてるの」
確定給付企業年金の予定利率とは?積立不足が起こる原因と対策
予定利率の2つの意味
「DBの話でよく『予定利率』って聞くんですが、これって何ですか?」
「実は予定利率には2つの意味があるの。これがDBを理解する上でとても重要なポイントよ」
予定利率の2つの意味
1. 財政運営上の予定利率
- ・掛金計算時に使用する運用収益の想定利率
- ・企業が決定し、厚生労働大臣が承認
- ・下限:10年国債利回りの5年平均または1年平均の低い方
2. 一般勘定の保証利率(予定利率)
- ・生命保険会社が保証する運用商品の利率
- ・保険会社が決定
- ・最近の引き下げ例:第一生命0.25%、日本生命0.50%
「えー!2つも意味があるんですか?」
「そうなの。だから『予定利率引き下げ』のニュースを見ても、どちらの意味かをちゃんと理解しないと誤解しちゃうのよ」
積立不足が発生する仕組み
「DBでよく『積立不足』って聞きますが、具体的にはどういう状況ですか?」
「これは重要な話ね。DBの財政運営の核心部分よ」
積立不足発生のメカニズム
| 正常な状態 | 積立不足の状態 |
|---|---|
| 年金資産 ≧ 責任準備金 | 年金資産 < 責任準備金 |
積立不足の主な原因
- 運用成績の悪化:予定利率を下回る運用実績
- 金利環境の変化:割引率低下による債務増加
- 人口統計の変化:平均寿命延伸による支払期間延長
- 給与水準の変化:想定を上回る昇給による債務増加
「つまり、予定していた前提と実際の状況がずれると、積立不足が起きるってことですね」
「その通り。そして積立不足が起きたら、企業が追加拠出しなければならないの」
財政検証の2つの基準
継続基準と非継続基準
DBでは年1回、財政状況をチェックする「財政検証」が義務付けられています。
継続基準
- ・制度を今後も継続することを前提とした検証
- ・積立不足が許容限度を超えると特別掛金で解消
非継続基準
- ・制度を今すぐ終了する場合を想定した検証
- ・最低積立基準額(給付現価の90-100%)を下回ると即座に対応
「2段階でチェックしてるんですね。安全装置が2つあるって感じ」
「そうよ。でも現実には、積立不足が発生すると企業の財政負担が重くなるから、最近はリスクを軽減する仕組みも導入されてるの」
現代的なリスク管理手法|リスク対応掛金とキャッシュバランスプラン
リスク対応掛金という新しい仕組み
「積立不足のリスクを軽減する仕組みって、どんなものですか?」
「一つは『リスク対応掛金』っていう仕組みよ。これは比較的新しい制度で、すごく実用的なの」
リスク対応掛金の仕組み
- 事前リスク測定:将来発生するリスクを「財政悪化リスク相当額」として測定
- 平準的拠出:20年に1回程度発生する損失を想定し、事前に掛金として拠出
- 積立不足の回避:不況期の掛金増加を回避し、安定的な財政運営
具体的な効果
従来:運用悪化時に追加拠出が必要
リスク対応掛金導入後:事前に積み立てているので追加拠出不要
「なるほど、『備えあれば憂いなし』を制度化したって感じですね」
「まさにその通り!不測の事態に備えて、平常時から少し多めに積み立てておく仕組みよ」
キャッシュバランスプランの詳細メカニズム
「もう一つ、最近よく聞く『キャッシュバランスプラン』についても教えてください」
「これも重要な仕組みね。確定給付の安心感を保ちながら、リスクを軽減する画期的な設計よ」
キャッシュバランスプランの基本構造
従来のDB
給付額 = 基本給 × 勤続年数 × 支給率(固定)
キャッシュバランスプラン
給付額 = 持分付与額 + 利息付与額(指標連動)
キャッシュバランスの特徴
- 仮想個人勘定:従業員ごとに個別の口座残高を管理
- 指標連動:利息付与額が国債利回り等の市場指標に連動
- 透明性:個人の積立状況が明確
- リスク軽減:金利変動リスクを従業員と企業で分担
退職給付債務安定化効果の仕組み
「キャッシュバランスプランの最大のメリットは、退職給付債務の安定化効果なの」
債務安定化効果のメカニズム
低金利時
- ・割引率低下 → 退職給付債務増加
- ・同時に指標利率低下 → 給付見込額減少
- ・結果:債務増加が相殺される
高金利時
- ・割引率上昇 → 退職給付債務減少
- ・同時に指標利率上昇 → 給付見込額増加
- ・結果:債務減少が相殺される
「金利が上がっても下がっても、影響が打ち消し合うんですね!すごい仕組み」
「そうなの。だから多くの企業がキャッシュバランスプランを採用してるのよ。企業年金の『いいとこ取り』って感じね」
一般勘定運用の実態と予定利率引き下げの影響
生保一般勘定の運用実態
「ところで、DBの運用で『一般勘定』ってよく聞くんですが、これは何ですか?」
「一般勘定は生命保険会社が提供する運用商品で、元本と一定利率を保証してくれるの。でも最近、大きな変化が起きてるのよ」
主要生保の予定利率引き下げ状況
| 生命保険会社 | 引き下げ時期 | 旧予定利率 | 新予定利率 |
|---|---|---|---|
| 第一生命 | 2021年10月 | 1.25% | 0.25% |
| 日本生命 | 2023年4月 | 1.25% | 0.50% |
| その他大手 | 検討中 | 1.25% | 未定 |
「えー!こんなに下がってるんですか?」
「そうなの。長期金利の低下で、生保会社も従来の利率を維持できなくなってるの。これがDB制度にも大きな影響を与えてるのよ」
予定利率引き下げが企業に与える影響
企業への具体的な影響
- 運用収益の低下:想定していた運用益が確保できない
- 掛金の増加:不足分を掛金で補う必要
- 制度見直しの検討:給付設計の変更や他制度への移行
企業の対応選択肢
| 対応策 | 内容 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 資産構成見直し | より高いリターンを狙う運用 | 収益向上の可能性 | リスク増加 |
| 掛金増額 | 不足分を掛金で補填 | 確実性 | コスト増加 |
| 給付減額 | 将来の支給額を引き下げ | コスト削減 | 従業員の反発 |
| 制度移行 | DCや他制度への移行 | リスク回避 | 移行コスト |
「生保の都合で企業も影響を受けるんですね…」
「そうなの。だからこそ、運用先の分散とか、制度設計の工夫が重要になってくるの」
ALM(資産負債管理)とポートフォリオ戦略
DBにおけるALMの重要性
「DBの運用で『ALM』って聞いたことがあるんですが、これはどういう意味ですか?」
「ALMはAsset Liability Managementの略で、資産と負債を一体的に管理する手法よ。DBでは特に重要な概念なの」
ALMの基本的な考え方
従来の運用:資産サイドのみに注目
- 資産 → どう増やすか?
ALMアプローチ:資産と負債の両方を管理
- 資産 ↔ 負債 → どうマッチングさせるか?
DBに適した資産配分の考え方
一般的なDB資産配分例
| 資産クラス | 配分目安 | 役割 | リスク特性 |
|---|---|---|---|
| 国内債券 | 40-60% | 安定収益の確保 | 低リスク・低リターン |
| 国内株式 | 15-25% | 成長性の追求 | 中リスク・中リターン |
| 外国債券 | 10-20% | 分散効果 | 中リスク・為替リスク |
| 外国株式 | 10-20% | 高成長の追求 | 高リスク・高リターン |
| オルタナティブ | 0-10% | 分散効果 | 多様なリスク |
「債券の比重が高いんですね」
「そうなの。DBは長期にわたって安定した給付を約束しなければならないから、安定性を重視した配分になるのよ」
リスク予算管理の実際
リスク予算の設定例
- ・許容損失額:資産の10%以内
- ・VaR(バリューアットリスク):95%信頼区間で年間5%以内
- ・トラッキングエラー:ベンチマークとの乖離3%以内
「リスクを数値で管理してるんですね」
「そうよ。感覚的な運用ではなく、きちんと数値で管理することで、想定外の損失を防いでるの」
リスク分担型企業年金という新しい選択肢
従来DBの限界を克服する仕組み
「最近『リスク分担型企業年金』という制度があるって聞いたんですが…」
「それはとても新しい仕組みよ。DBのメリットを保ちながら、企業のリスクを軽減する画期的な制度なの」
リスク分担型企業年金の基本構造
従来のDB
- ・企業が運用リスクを100%負担
- ・積立不足時は企業が追加拠出
リスク分担型
- ・企業:リスク対応掛金の範囲内でリスクを負担
- ・従業員:それを超える部分は給付調整で負担
調整率による給付変動
| 積立状況 | 調整率 | 給付への影響 |
|---|---|---|
| 積立剰余 | 1.0超 | 給付額増加 |
| 財政均衡 | 1.0 | 通常給付 |
| 積立不足 | 1.0未満 | 給付額減少 |
「企業と従業員でリスクを分け合うんですね」
「そうなの。企業にとっては予測可能な範囲でリスクを負担し、従業員にとっては一定の給付保障がある。まさに『いいとこ取り』の制度よ」
退職給付会計上の取扱い
「リスク分担型の大きなメリットは、退職給付会計上の取扱いなの」
会計上の分類
- 従来のDB:確定給付制度 → 退職給付債務を計上
- リスク分担型:確定拠出制度 → 拠出時費用処理のみ
「会計上は確定拠出扱いなんですか!」
「そうなの。企業に追加拠出義務がないから、確定拠出制度として取り扱われるの。これは企業にとって大きなメリットよ」
まとめ:DB制度の奥深さと現代的な進化
DBについて学んで分かったこと
サキ先輩に詳しく教えてもらって、DBの全体像と複雑さがよく理解できました。
DBの本質的な特徴
- 🔶従業員にとっては安心感のある確定給付
- 🔶企業にとっては複雑な財政運営と運用リスク
- 🔶制度設計次第でリスク軽減が可能
- 🔶現代的な手法により柔軟性と安定性を両立
現代DBの進化ポイント
- ✅リスク対応掛金:事前のリスク準備
- ✅キャッシュバランスプラン:債務安定化効果
- ✅リスク分担型:企業と従業員でのリスク分担
- ✅ALM手法:資産負債の一体管理
DCとDBの本質的な違いの理解
今日の学習で、DCとDBの本質的な違いがクリアになりました。
運用リスクの所在
- DC:従業員が100%負担 → 投資知識と関心が必須
- DB:企業が負担 → 専門的な運用管理が必要
制度の複雑さ
- DC:シンプルな拠出・運用・給付
- DB:財政検証・予定利率・積立管理等の高度な仕組み
従業員の関与
- DC:商品選択・運用指図が必要(でも実際は無関心)
- DB:基本的に関与不要(でも制度理解は重要)
「サキ先輩、ありがとうございました。DBの仕組みがよく分かりました。特に最近の進化した仕組みがすごく興味深かったです」
「どういたしまして。DBは確かに複雑だけど、それだけ従業員のことを考えて作られた制度なのよ。次は中退共についても調べてみると、退職金制度の全体像がより見えてくるわ」
「はい!3つの制度を比較できるようになったら、うちの会社にとって最適な制度も見えてきそうです」
会社と従業員の両方にとってベストな選択をすることが大切よ
DBの奥深さを知ることで、退職金制度選択の重要性を改めて実感しました。単に「お金を積み立てる」だけでなく、長期的な視点での制度設計や運営管理が重要だということがよく分かりました。
次は中小企業退職金共済について調べて、3つの制度の特徴を整理してみたいと思います。従業員の安心と企業の持続性、両方を考えた制度選択ができるよう、しっかり勉強していこう!

プロフィール
名前: ユキ
年齢: 24歳(第1回スタート時)
所属: IT企業 人事部(従業員150名規模)
中小企業の人事担当者として、従業員の幸せと会社の成長を両立させる制度づくりに挑戦中
【ご注意】 本記事は、中小企業の人事担当者「ユキ」の成長を描いたフィクションです。登場する企業名、人物、具体的な数値変化の事例などは、説明をわかりやすくするための創作です。
ただし、以下の情報は実際のデータに基づいています:
- 厚生労働省・企業年金連合会等の公的機関の統計データ
- 確定給付企業年金制度の仕組みや法的根拠
- 予定利率・積立不足・財政検証等の制度運営に関する情報
- リスク管理手法や現代的な給付設計に関する情報
実際の制度利用や導入を検討される際は、専門家にご相談の上、企業・従業員の状況に応じた判断を行ってください。
YUKINつみたてDBプランのご案内
月額1,000円から始められる確定給付企業年金制度です。キャッシュバランスプランによる債務安定化効果と、選択制による企業負担軽減を両立した、現代的なDB制度です。

今すぐご相談・資料請求
YUKINのことがよくわかる資料を無料ダウンロードいただけます!
また無料面談も行っておりますので、お問い合わせフォームよりお気軽にお申し込みください。
よくあるご質問
確定給付企業年金で積立不足が発生したらどうなりますか?
継続基準で許容限度を超えた場合は特別掛金での解消、非継続基準で最低積立基準額を下回った場合は即座に追加拠出が必要となります。
ただし、リスク対応掛金等の事前対策で回避可能です。予定利率とは何ですか?
予定利率には①財政運営上の予定利率(掛金計算に使用)②一般勘定の保証利率の2つの意味があります。
記事本文中の「予定利率引き下げ」は主に②を指しています。キャッシュバランスプランのメリットは何ですか?
金利変動に対する退職給付債務の安定化効果が最大のメリットです。
国債利回り等の指標に連動することで、割引率変動による債務増減を自動的に相殺します。リスク分担型企業年金とは何ですか?
企業と従業員で運用リスクを分担する新しいDB制度です。
企業はリスク対応掛金の範囲でリスクを負担し、それを超える部分は給付調整で従業員が負担します。
退職給付会計上は確定拠出制度として扱われます。DBの運用はどのように行われますか?
ALM(資産負債管理)手法により、将来の給付債務とのマッチングを考慮した運用を行います。
一般的には国内債券を中心とした安定性重視のポートフォリオが採用されます。