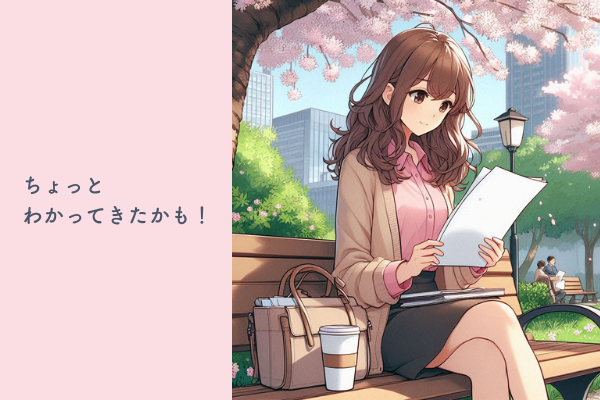【第4回】退職金制度の導入費用はいくら?中小企業の初期投資と運用コスト
目次
退職金制度の費用って実際どのくらい?
前回、サキ先輩とのランチで4つの退職金制度(DB、DC、中退共、退職一時金)の特徴を勉強した私。
次に知りたくなったのは、やっぱり費用のこと。
「制度の違いはわかったけど、実際いくらかかるんだろう?」
人事部のデスクで、パソコンに向かって調査開始。
でも、ネットで調べても「詳細はお問い合わせください」「企業規模により異なります」ばかり…。
具体的な数字が知りたい!
思い切って、実際に何社かの金融機関や運営管理機関に電話してみることにしました。
「あの、退職金制度について教えていただきたいんですが…」
退職金制度の初期費用|想定外の項目が続々
掛金だけじゃない初期投資
「従業員150名のIT企業ですが、退職金制度の導入を検討していて…」
電話で問い合わせると、各社の営業担当者が詳しい資料を送ってくれました。
そこで初めて知ったのが、掛金以外にもいろいろな費用がかかるということ。
ある信託銀行からの見積もり例(DB制度の場合)
| 項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 制度設計費 | 100-200万円 | 給付設計、掛金計算 |
| 数理計算費用 | 50-80万円 | 将来の給付債務の算定 |
| 規約作成・認可申請 | 30-50万円 | 厚生労働省への申請書類 |
| システム対応 | 50-150万円 | 既存システムとの連携 |
| 初期費用合計 | 230-480万円 | – |
しかも、これは初期費用だけ。毎年の運営費用は別途必要とのこと。
一方、中退共の場合は、
- ・加入申込書の作成:基本無料
- ・就業規則の改定:10-20万円程度(社労士に依頼する場合)
この差は大きい!でも、前回学んだとおり、それぞれメリット・デメリットがあるから、費用だけで決めるわけにはいかない。
毎月の掛金額をどう設定するか
まず相場を調べてみた
掛金額っていくらが妥当なんだろう?
調べてみると、一般的には、都内中小企業では基本給の3-5%程度を退職金掛金とする企業が多いみたい。
うちの会社の平均基本給が25万円だとすると、
- ・3%なら:7,500円/人
- ・4%なら:10,000円/人
- ・5%なら:12,500円/人
でも待って。これをいきなり始めるのは現実的?
月1万円で計算すると(従業員150人)、
- ・月額:150万円
- ・年額:1,800万円
うーん、これは結構な負担…。
段階的導入の現実性
そこで、段階的に増やしていく案を考えてみました。実際、問い合わせた金融機関の担当者も「最初は少額から始める企業が多いですよ」と言っていました。
段階的導入案の検討
| 開始時の掛金 | 月額総額 | 年額総額 | 5年後目標 |
|---|---|---|---|
| 月2,000円/人 | 30万円 | 360万円 | 月7,000円 |
| 月3,000円/人 | 45万円 | 540万円 | 月10,000円 |
| 月5,000円/人 | 75万円 | 900万円 | 月15,000円 |
最初は月2,000-3,000円から始めて、業績や効果を見ながら増額していく。これなら現実的かも。
運営管理費用の比較
制度ごとの年間コスト
掛金以外にも、毎年かかる運営管理費用があることがわかりました。
年間運営費用の比較(従業員150人の場合)
| 制度 | 年間費用 | 主な内訳 |
|---|---|---|
| DB | 80-250万円 | 信託報酬、数理計算、財政検証 |
| DC | 50-150万円 | 運営管理機関手数料、投資教育 |
| 中退共 | ほぼ0円 | 振込手数料程度 |
| 退職一時金 | 0-20万円 | 外部委託する場合のみ |
DBは毎年の数理計算(財政再計算)が法令で義務付けられていて、これだけで年30-50万円かかるとのこと。
「中小企業にはハードルが高いですね…」と正直に金融機関の人に言ったら、「最近は中小企業向けの簡易型DBも出てきてますよ」と教えてくれました。
中退共の助成金制度を詳しく調査
新規加入助成の威力
中退共の最大の魅力は、なんといっても助成金。詳しく調べてみました。
<中退共の新規加入助成>
- 加入後4か月目から1年間、
- 掛金月額の1/2(上限5,000円)を助成
出典: 中小企業退職金共済事業本部
助成金シミュレーション(月5,000円の掛金、150人加入)
| 期間 | 掛金総額 | 助成金額 | 実質負担 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 900万円 | 450万円 | 450万円 |
| 2年目以降 | 900万円 | 0円 | 900万円 |
初年度は実質半額!これは大きい。
ただし、注意点も・・・
- ・2年目から負担が倍増
- ・掛金納付月数が12か月未満だと退職金が支給されない
- ・懲戒解雇でも減額できない
- ・掛金上限は月3万円まで
「うちは離職率18%だから、1年未満で辞める人の掛け捨てリスクも考慮しないと…」
中退共は助成金が魅力的だけど、制約も多いんだな。
節税効果を含めた実質コスト
法人税の削減効果
経理部で教えてもらった節税効果についても計算してみました。
退職金の掛金は全額損金算入可能。法人税率を約30%とすると・・・
節税効果シミュレーション
| 年間掛金 | 法人税削減額 | 実質負担 | 負担率 |
|---|---|---|---|
| 360万円 | 108万円 | 252万円 | 70% |
| 540万円 | 162万円 | 378万円 | 70% |
| 900万円 | 270万円 | 630万円 | 70% |
| 1,800万円 | 540万円 | 1,260万円 | 70% |
つまり、実質的には掛金の70%の負担で済むということ。
ただし、経理部からは「節税効果は決算後に実現するから、キャッシュフローは100%出ていくよ」との指摘も。確かに、資金繰りは別問題だ。
選択制という選択肢の発見
会社の掛金負担がゼロ?
調査を進める中で、興味深い仕組みを知りました。
「選択制退職金制度」というものがあるらしい。金融機関の担当者が教えてくれました。
「選択制なら、従業員が自分の給与から積み立てる形なので、会社の掛金負担はゼロにすることも可能です」
「え?会社が払わなくていいんですか?」
「従業員が給与の一部を退職金として積み立てるか、そのまま給与として受け取るかを選択できる制度です。会社は追加の掛金負担なしに退職金制度を導入できます」
なるほど、こういう方法もあるんだ!
詳しく聞いてみると、従業員にとっては、
| メリット | ・積立金は給与として課税されない(所得税・住民税の削減) ・社会保険料も減る(手取りの減少を緩和) ・自分で老後資金を計画的に準備できる |
| デメリット | ・額面の手取りは減る ・社会保険料が減る分、将来の年金額にも影響 ・いつでも自由に引き出せるわけではない(退職時まで原則引き出せない) |
「つまり、税金や社会保険料の負担が減る分、実質的な手取りの減少は抑えられるんですね」
「そうです。だから従業員も積極的に選択する方が多いんですよ。ただし、メリット・デメリットをしっかり理解してもらう必要がありますね」
選択制については、もっと勉強が必要だな。今回は基本的な費用構造の理解に集中しよう。
費用対効果をどう評価するか
離職コスト削減との比較
以前計算した離職コスト(年間5,670万円)と比較してみました。
もし退職金制度導入で離職率が18%→15%(3ポイント改善)になったら・・・
- 削減人数:4.5人/年
- コスト削減:4.5人×210万円=945万円/年
年間掛金540万円(月3,000円×150人)に対して、945万円の削減効果。理論上は投資回収可能。
ただし、「退職金制度だけで離職率が下がるとは限らない」という現実も忘れずに。
まとめ:中小企業でも始められる現実的な方法
今日一日かけて退職金制度の費用について調査して、いろんな発見がありました!
📊 初期費用のリアル
- 中退共なら10万円程度でスタート可能!
- DBやDCは数百万円かかることも…でもパッケージ型なら削減できる
💰 掛金の現実的なライン
- いきなり月1万円は厳しい → 月2,000-3,000円から始めればOK!
- 段階的に増やしていけばいいんだ
🎁 助成金のインパクト
- 中退共なら初年度は掛金の半額助成(最大5,000円/人)
- でも1年限定だし、制約もあるから要注意
✨ 節税マジック
- 掛金は全額損金算入 → 実質負担は70%に!
- ただしキャッシュは先に出ていくから資金繰りは要チェック
🆕 選択制という新発見
- なんと会社の掛金負担ゼロも可能!?
- 従業員が自分で積み立てる仕組みもあるんだ
次のステップは、この調査結果を整理して、もっと深く理解すること。
正直なところ、どの制度がうちの会社に合うのか、まだ全然わからない…。
- ・中退共は助成金が魅力的だけど、制約も多い
- ・DBやDCは本格的だけど、費用が高い
- ・選択制は会社負担ゼロだけど、従業員への説明が大変そう
- ・退職一時金はシンプルだけど、倒産リスクが…
それぞれ一長一短があって、簡単には決められないんだな。
費用も大事だけど、「従業員の将来を守る」という想いを忘れずに。でも同時に、会社が潰れたら元も子もない。
バランスが大切。それが中小企業の退職金制度設計なんだ!
まだまだ勉強することはたくさんあるけど、少しずつ全体像が見えてきた気がする。次は、この制度が本当に離職防止に効果があるのか、もっと深く調べてみたいな。

プロフィール
名前: ユキ
年齢: 24歳(第1回スタート時)
所属: IT企業 人事部(従業員150名規模)
中小企業の人事担当者として、従業員の幸せと会社の成長を両立させる制度づくりに挑戦中
【ご注意】 本記事は、中小企業の人事担当者「ユキ」の成長を描いたフィクションです。登場する企業名、人物、具体的な数値変化の事例などは、説明をわかりやすくするための創作です。
ただし、以下の情報は実際のデータに基づいています:
- 中退共の助成金制度
- 退職金制度の仕組みや税制
- 法令に関する情報
実際の効果は企業の規模、業種、地域、その他の要因により異なります。退職金制度の導入を検討される際は、専門家にご相談の上、自社の状況に応じた制度設計を行ってください。
YUKINつみたてDBプランのご案内
月額1,000円から始められる確定給付企業年金制度です。中小企業でも導入しやすく、段階的な拡充も可能です。

今すぐご相談・資料請求
YUKINのことがよくわかる資料を無料ダウンロードいただけます!
また無料面談も行っておりますので、お問い合わせフォームよりお気軽にお申し込みください。
よくあるご質問
中退共の助成金はどの企業でも受けられる?
中退共の助成金は、加入条件(従業員数・資本金)を満たす中小企業なら受けられます。ただし、助成は1年間限定で、2年目以降は全額自己負担になります。
節税効果と資金繰りの関係は?
掛金の約30%が法人税削減として戻りますが、これは決算後。
まず100%の掛金を支払う必要があるため、資金繰りへの影響は避けられません。