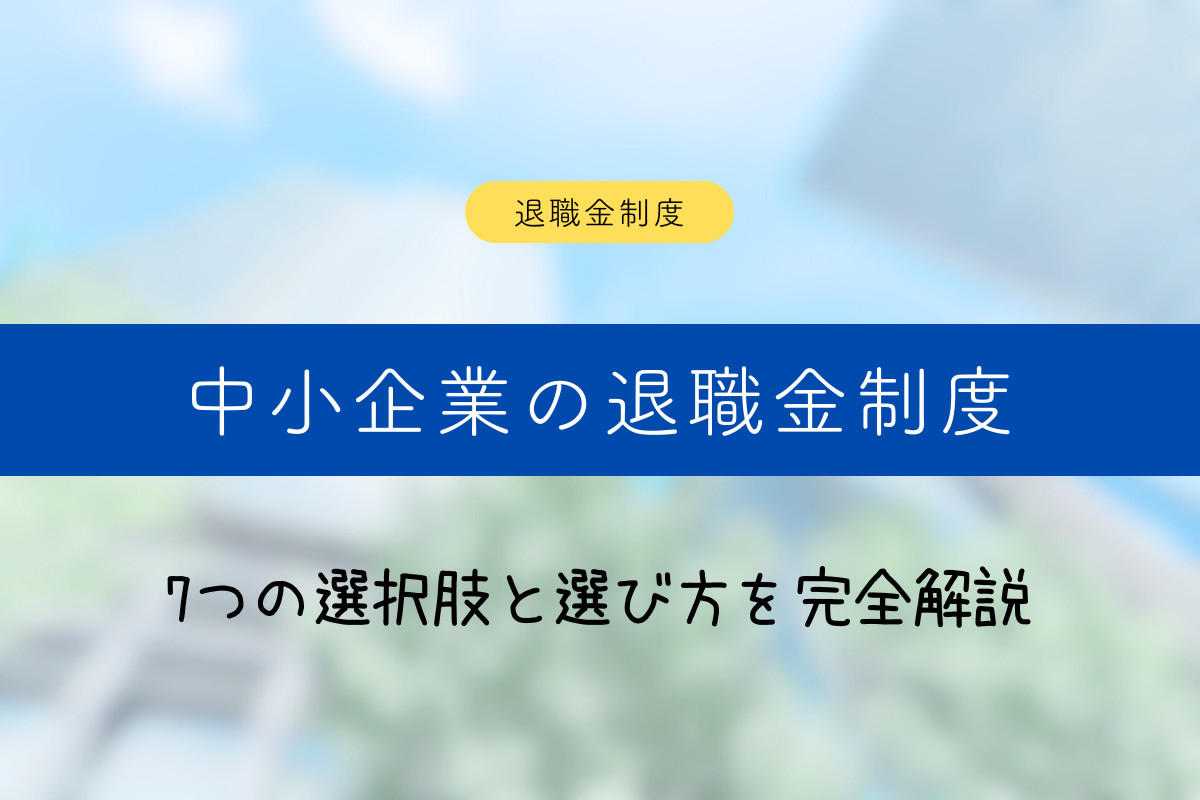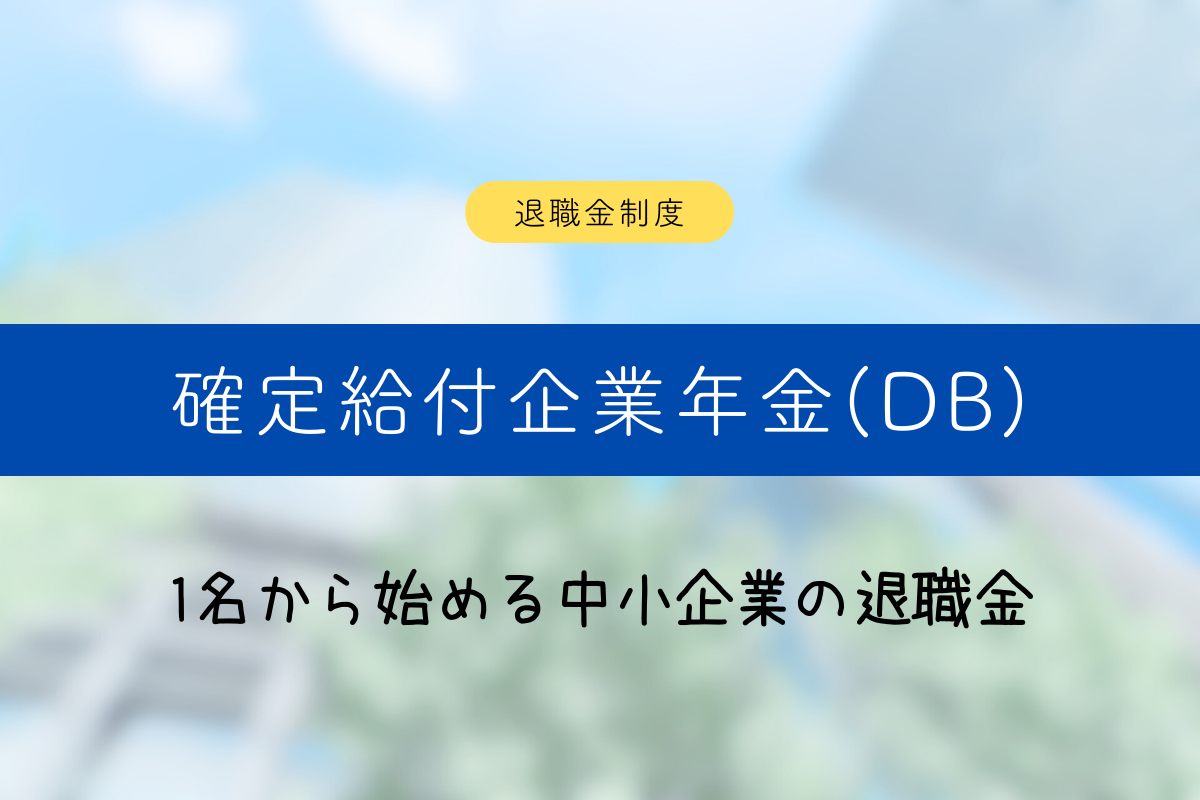中小企業の退職金制度|7つの選択肢と選び方を完全解説
中小企業における退職金制度は、従業員の定着率向上や離職率の改善だけでなく、福利厚生の充実、人件費の戦略的な再配分など、複数の経営課題を同時に解決できる重要な制度です。人材不足が深刻化する中、優秀な人材の確保と定着は企業の競争力に直結します。
本記事では、中小企業が導入できる7つの退職金制度(退職一時金、確定給付企業年金、確定拠出年金、中小企業退職金共済、小規模企業共済、iDeCo+、選択制退職金制度)について、それぞれのメリット・デメリット、導入コスト、手続きの流れまで詳しく解説します。企業規模や業種、経営方針に応じた最適な制度選びの指針もご提供します。
特に注目すべきは、選択制退職金制度「YUKINつみたてDBプラン」です。選択制により従業員が自分のニーズに応じて給与から積立額を選べるため、賃上げ要請への対応と将来への備えを両立できます。完全選択制なら会社の掛金負担はなく、社会保険料負担の軽減効果も期待でき、限られた人件費予算を効率的に活用できる点も中小企業にとって大きなメリットとなります。
中小企業に退職金制度が必要な3つの理由
1. 中小企業の70%がすでに導入している
まず、実際のデータを見てみましょう。
| 企業規模 | 導入率 |
|---|---|
| 1,000人以上 | 92.3% |
| 300~999人 | 88.8% |
| 100~299人 | 84.7% |
| 30~99人 | 70.1% |
中小企業でも10社中7社が退職金制度を持っています。もはや「あったらいい」ではなく「なければ不利」という状況です。
業種別で見ると、製造業が82.1%でトップ、次いでIT・情報通信業の74.6%。一方、宿泊業・飲食サービス業は42.2%と業種によって大きな差があります。
2. 求職者の42.8%が退職金制度を重視している
マイナビキャリアリサーチLabの「転職動向調査2025年版」によると、2024年に転職した人が応募意欲が上がる制度・施策として最も多く挙げたのが「退職金制度がある」で42.8%でした。
応募意欲が高まる制度・人事施策(上位5項目)
| 順位 | 制度・施策 | 割合 |
|---|---|---|
| 1位 | 退職金制度がある | 42.8% |
| 2位 | 有給取得率向上施策 | 34.5% |
| 3位 | 企業独自の休暇制度 | 32.9% |
| 4位 | 社内公募制度がある | 32.1% |
| 5位 | 在宅勤務制度や通信費・補助する制度 | 30.5% |
マイナビキャリアリサーチLab「転職動向調査2025年版(2024年実績)」
退職金制度は「長く働くメリット」を目に見える形で示せます。人材獲得競争が激化する今、退職金制度の有無は企業の採用力を大きく左右しているのです。
3. 掛金は全額損金となり、人件費の圧縮効果もある
退職金制度には、見逃せない税務上のメリットがあります。
適切に設計された退職金の積立金は、全額損金算入が可能です。具体的な節税効果を見てみましょう。
節税効果シミュレーション(従業員10名の場合)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 従業員数 | 10名 |
| 月額掛金(1人あたり) | 10,000円 |
| 月額掛金総額 | 100,000円 |
| 年間掛金総額 | 1,200,000円 |
| 法人実効税率 | 約30% |
| 年間節税効果 | 約360,000円 |
さらに、選択制退職金制度を採用した場合、労使双方の社会保険料負担が軽減されることがあります。これは、従業員が給与の一部を退職金積立に振り替える「選択制」の仕組みによるもので、社会保険料を算定する標準報酬月額が下がることで得られる副次的な効果です。
ただし、適切な制度設計が不可欠です。税法上の要件を満たさないと思わぬ税務リスクを抱えることになるため、専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めします。
中小企業が選べる7つの退職金制度
中小企業が導入できる退職金制度は大きく分けて7つ。それぞれに特徴があり、企業の規模や業種、経営方針によって最適な制度は異なります。
1. 退職一時金制度|最も基本的な選択肢
退職一時金制度は、企業が退職時に直接支払う最もシンプルな制度。多くの中小企業が最初に検討する選択肢です。
メリット
- ✅ 初期投資が不要で、すぐに始められる
- ✅ 制度設計の自由度が高い
- ✅ 外部機関への手数料が発生しない
- ✅ 懲戒解雇時の不支給など、柔軟な運用が可能
デメリット
- ❌ 退職時に一度に大きな資金が必要
- ❌ 企業が倒産した場合、支払いが保証されない
- ❌ 計画的な資金準備が必要
退職一時金制度は、「基本給×勤続年数×支給率」といった独自の計算式を設定できます。しかし実際のところ、多くの中小企業では帳簿上は退職金引当金を計上していても、実際の現金準備ができていないケースが少なくありません。
適している企業:キャッシュフローが安定していて、計画的な資金準備ができる企業。特に従業員数が10名以下で、平均年齢が若い企業には向いています。
2. 確定給付企業年金(DB)|給付額保証の安心感
DBは、将来の給付額をあらかじめ約束する年金制度です。企業が掛金を拠出し、運用リスクも企業が負うため、従業員にとって最も安心感のある制度といえます。
メリット
- ✅ 従業員にとって給付額が保証されている安心感
- ✅ 運用は専門機関に任せられる
- ✅ 税制優遇が充実している
デメリット
- ❌ 運用リスクを企業が負う
- ❌ 積立不足が発生した場合、追加拠出が必要
- ❌ 導入・運営コストが高額
企業は信託銀行や生命保険会社と契約を結び、掛金を拠出します。
将来の給付額は勤続年数や給与水準に基づいて決定され、運用成果に関わらず、約束された金額が支給されます。
従業員数50名以上の中堅企業で、財務基盤が安定しており、長期的な視点で人材戦略を考えている企業に適しているといえます。
3. 確定拠出年金(DC)|自己責任型の資産形成
DCは、企業が掛金を拠出し、従業員自身が運用指図を行う制度です。最終的な給付額は運用成果によって変動するため、従業員が運用リスクを負う仕組みとなっています。
メリット
- ✅ 企業にとって追加拠出のリスクがない
- ✅ ポータビリティが高く、転職時も継続可能
- ✅ 税制優遇(掛金非課税、運用益非課税、受取時の控除)
デメリット
- ❌ 従業員が運用リスクを負う(元本割れの可能性)
- ❌ 原則60歳まで引き出せない
- ❌ 投資教育が必須となる
企業は毎月一定額の掛金を拠出し、従業員個人の口座に積み立てます。従業員は、用意された金融商品(投資信託など)の中から自由に選んで運用し、60歳以降に運用成果に応じた金額を受け取ります。
適している企業:IT企業など従業員の金融リテラシーが高い企業や、将来の退職金債務を確定させたい企業。
4. 中小企業退職金共済(中退共)|国の支援制度
中退共は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する、中小企業のための退職金制度です。全国約37万事業所、355万人が加入している実績があります(令和5年3月末現在)。
メリット
- ✅ 管理の手間がかからない(共済機構が運営)
- ✅ 掛金は全額損金算入可能
- ✅ 企業が倒産しても退職金は保護される
- ✅ 新規加入時の助成金がある(掛金月額の1/2、上限5,000円を1年間)
デメリット
- ❌ 掛金は16種類の固定額のみ(5,000円~30,000円)
- ❌ 12か月未満の退職では退職金ゼロ
- ❌ 24か月未満では元本割れ
- ❌ 役員は原則加入できない
適している企業:従業員10~50名程度で、安定的な制度運営を重視する企業。国の助成を活用できる点は大きな魅力ですが、短期退職時のデメリットも考慮する必要があります。
5. 小規模企業共済|経営者・役員のための制度
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の役員が自分の退職金を準備するための制度です。中小企業基盤整備機構が運営しており、全国約162万人が加入しています。
メリット
- ✅ 掛金全額が所得控除(年間最大84万円)
- ✅ 月額1,000円~70,000円まで500円単位で自由設定
- ✅ 共済金受取時も退職所得控除等の税制優遇
- ✅ 低利の貸付制度も利用可能
デメリット
- ❌ 従業員は加入できない(役員・個人事業主のみ)
- ❌ 20年未満の解約は元本割れのリスク
- ❌ 加入条件が厳格(従業員20名以下等)
加入条件
- 常時使用する従業員が20名以下(商業・サービス業は5名以下)の個人事業主または会社役員
活用方法:従業員の退職金制度(中退共やYUKINなど)と併用することで、経営者も含めた総合的な退職金制度を構築できます。
6. iDeCo+(イデコプラス)|中小企業向けの新選択肢
iDeCo+は、従業員300人以下の中小企業が、従業員のiDeCo掛金に上乗せ拠出できる制度です。2018年に創設された比較的新しい制度で、中小企業の退職金制度の選択肢を広げています。
メリット
- ✅ 既存のiDeCoを活用するため、新たな制度設計が不要
- ✅ 拠出した掛金は全額損金算入
- ✅ 企業型DCより運営コストが低い
- ✅ 従業員の自主性を尊重できる
デメリット
- ❌ 従業員がiDeCoに加入していることが前提
- ❌ 労使合意が必要
- ❌ 事業主による掛金の取りまとめ事務が発生
従業員が加入しているiDeCoに対し、事業主が月額1,000円から23,000円の範囲で掛金を上乗せします。従業員の掛金と事業主の掛金の合計は月額23,000円が上限となります。
適している企業:企業型DCを導入するほどの規模ではないが、従業員の資産形成を支援したい企業。特に従業員の自主性を重視する企業文化がある場合。
7. 【注目】YUKINつみたてDBプラン|選択制退職金制度の決定版
YUKINつみたてDBプランは、2022年に設立された総合型確定給付企業年金基金「ゆうきん企業年金基金」が提供する、中小企業向けに特化した選択制退職金制度です。
YUKINが選ばれる5つの理由
- 生涯賃金における手取り向上:税金や社会保険料の負担減少により、生涯賃金での実質的な手取りが向上
- 従業員1名から導入可能:役員や経営者も加入でき、小規模企業でも始めやすい
- 完全選択制なら会社の掛金負担なし:従業員が給与から選択して積立
- 導入・運用が簡単:サポートが手厚い
- 法定福利費の抑制効果:社会保険料の会社負担分を軽減
YUKINと他制度の比較
| 比較項目 | YUKIN | 中退共 | iDeCo+ |
|---|---|---|---|
| 任意加入 | 可能 | 不可(全員加入) | 可能 |
| 加入年齢 | 70歳未満 | 制限なし | 65歳未満 |
| 役員加入 | 可能 | 不可 | 可能 |
| 会社の掛金負担 | 選択制なら不要 | あり | あり |
| 従業員の拠出額 | 1,000円〜給与の20%<br>(最大30万円) | - | 個人拠出あり |
| 会社拠出(選択制以外) | 1,000円〜 | 5,000円〜30,000円<br>(16段階) | 1,000円〜22,000円 |
| 社会保険料の負担軽減効果 | 軽減可能(※) | 軽減不可 | 軽減不可 |
| 資産運用 | 基金による管理・運用 | 機構による管理・運用 | 加入者が運用 |
| 積立金の受取可能時期 | 退職時、休職時 | 退職時 | 60歳以降 |
※ 選択制退職金制度の導入に伴い発生する副次的効果です。
自社に最適な退職金制度の選び方
退職金制度の計算方法から考える制度選択
退職金制度を選ぶ際は、制度の種類だけでなく「どのような計算方法にするか」も重要な検討要素です。その計算方式によって従業員への影響や企業の負担が大きく変わります。
計算方式による特徴の違い
- 基本給連動型:分かりやすく長期勤続にインセンティブ
- 定額制:コスト予測が容易でシンプル運用
- ポイント制:成果や貢献度を柔軟に反映
- 選択制:従業員のライフプランに応じた個別対応
自社の人事制度や企業文化に適した計算方式により制度選択することで、より効果的な退職金制度を構築できます。
従業員規模から考える制度選択
退職金制度を選ぶときは、まず自社の従業員規模から考えていきましょう。
小規模企業(30名以下)では、中退共やYUKINのような外部機関が運営を代行する制度がおすすめです。特に10名以下の企業なら、選択制のYUKINを使えば会社の掛金負担なしで始められ、役員も加入できるため、全員をカバーする制度設計ができます。
中規模企業(31~100名)になると、複数制度の併用も視野に入ってきます。例えば、基本部分を中退共でカバーし、追加部分をYUKINで補完するといった組み合わせです。この規模になると、兼任でも退職金担当者を置いて、制度運営を安定化させることが大切です。
従業員が100名を超えてくると、DBやDCといった本格的な制度も選択肢に入ってきます。これらの制度は複雑に見えますが、制度によっては実務の代行やサポートが受けられるため、想像以上に導入・運営のハードルは低くなっています。重要なのは、財務基盤の安定性と、自社に合った制度を選択することです。
業種特性から考える制度選択
業種によって人材の流動性や雇用慣行が異なるため、それぞれに適した制度設計が必要です。
IT・スタートアップ企業
人材の流動性が高く、20代~30代の若手が中心。転職が当たり前の文化があり、終身雇用を前提としない雇用形態が一般的です。また、成果主義的な報酬体系を採用している企業が多い傾向にあります。
制度選択のポイント
- ポータビリティの確保:DCやYUKINなど、転職時も継続できる制度
- 短期退職への配慮:中退共の24ヶ月未満元本割れは大きなデメリット
- 選択の自由度:選択制により個人のニーズに対応できる仕組み
- 柔軟な掛金設定:給与水準やライフステージに応じた調整が可能
製造業
長期勤続を前提とした雇用慣行が根強く、熟練技術者の確保・定着が経営課題。平均勤続年数が長く、年功序列的な要素も残っている企業が多い傾向にあります。
制度選択のポイント
- 勤続インセンティブ:勤続年数に応じて退職金が大きく増える設計
- 給付額の予測可能性:DBや中退共など、将来の受取額が明確な制度
- 安定性の重視:元本保証があり、従業員が安心できる制度
- 技術継承への配慮:ベテラン社員の処遇を手厚くする設計
サービス業
パート・アルバイトなど非正規雇用が多く、離職率が高い傾向。賃金水準が比較的低く、人件費コントロールが重要な経営課題となっています。
制度選択のポイント
- 早期積立の実現:短期間でも一定の退職金が積み立てられる制度
- 加入要件の柔軟性:正社員以外も加入できる制度設計
- コスト管理:選択制により人件費をコントロール
- 手続きの簡素化:入退社が多いため、事務負担が少ない制度
総合的な制度選択の5つの判断基準
従業員規模と業種特性を踏まえた上で、以下の5つの基準から総合的に判断します。
基準1:財務的な持続可能性
退職金制度は長期にわたる約束です。現在の資金余力だけでなく、将来の事業計画も含めて検討する必要があります。
- 現在のキャッシュフロー分析:月額掛金総額が売上高の何%になるか
- 将来の負担予測:従業員の増加や昇給を見込んだシミュレーション
- 選択制の活用:YUKINの選択制なら、会社の新たな負担なしで制度導入可能
基準2:人材戦略との整合性
退職金制度は企業の人材戦略を支える重要なツールです。
- 採用競争力の強化:同業他社と比較して遜色ない制度設計
- 定着率の向上:勤続インセンティブが働く制度設計
- 多様な働き方への対応:正社員以外も加入できる柔軟な制度
基準3:リスク管理の観点
制度選択には様々なリスクが伴います。これらを適切に管理することが重要です。
- 運用リスク:DBは企業が運用リスクを負う、DCは従業員が負う
- 積立不足リスク:DBでは追加拠出の可能性、中退共やYUKINなら不要
- 制度変更リスク:将来の不利益変更の難しさを考慮
基準4:従業員の理解と納得性
どんなに良い制度でも、従業員の理解と納得が得られなければ効果は半減します。
- 制度の分かりやすさ:複雑すぎない、説明しやすい制度
- 選択の自由度:YUKINのような選択制なら、個々のニーズに対応可能
- 透明性の確保:積立状況が確認できる仕組み
基準5:将来の発展性
企業の成長とともに、退職金制度も進化させる必要があります。
- 段階的な拡充可能性:掛金額の増額や制度の追加が容易か
- 他制度との併用:将来的に複数制度を組み合わせられるか
- 法改正への対応力:制度変更に柔軟に対応できる運営体制か
これらの基準を総合的に評価し、自社の状況に最も適した制度を選択することが、退職金制度導入成功の鍵となります。
退職金制度導入で失敗しないための注意点
よくある失敗パターン
退職金制度の導入で失敗する企業には、共通のパターンがあります。
1. 資金繰りを考慮しない導入
最も多い失敗は、資金繰りを十分に検討せずに制度を導入してしまうケースです。掛金の支払いだけを考えて導入したものの、社会保険料の会社負担分も含めると予想以上の負担となり、継続が困難になることがあります。
重要:助成金や節税効果は後から。キャッシュフローは先に支出が発生します。
2. 従業員への説明不足
従業員への説明が不十分なまま導入してしまうケースも多く見られます。特に選択制の制度では、社会保険料への影響など、複雑な仕組みを理解してもらう必要があります。
3. 制度を複雑にしすぎる
職階別、勤続年数別、評価別など、細かく設定しすぎると管理が煩雑になり、従業員にとってもわかりにくい制度になってしまいます。
成功のための3つのポイント
1. 段階的導入を検討する
最初から完璧な制度を作ろうとせず、段階的に充実させていくアプローチが有効です。
段階的導入の例
- 初年度:月額3,000円でスタート
- 2年目:月額5,000円に増額
- 3年目:月額10,000円に増額
企業の成長に合わせて無理なく拡充することで、失敗リスクを最小化できます。
2. 従業員との合意形成を丁寧に行う
- 導入前に従業員アンケートを実施
- 説明会を複数回開催(対面・オンライン併用)
- 質疑応答の時間を十分に確保
- 個別相談の機会も設ける
3. 専門家を活用する
- 社会保険労務士:制度設計から規程作成まで幅広くサポート
- 税理士:節税効果の試算や会計処理のアドバイス
- 制度運営機関:具体的な運用方法の指導
YUKINつみたてDBプランなら、専門スタッフが導入から運用まで全面サポートします。
まとめ:中小企業の成長戦略としての退職金制度
日本の雇用環境の大転換期
日本の労働市場は今、大きな転換期を迎えています。
終身雇用制度の見直しと新たな人材戦略
日本型雇用慣行の象徴であった終身雇用制度は、グローバル化の進展、デジタル化による産業構造の変化、少子高齢化による労働力不足など、複合的な要因により維持が困難になってきています。年功序列型の賃金体系から、ジョブ型雇用や成果主義への移行が進む中、企業は従業員との新たな関係性を模索しています。
このような環境下で、退職金制度は企業と従業員をつなぐ重要な役割を果たします。雇用の流動性が高まる中でも、退職金制度があることで従業員に長期的な視点を持ってもらい、企業への帰属意識を醸成できます。転職が当たり前の時代だからこそ、「この会社で長く働くメリット」を明確に示す必要があるのです。
賃上げ機運と人件費の戦略的再配分
2024年の春闘では平均賃上げ率が5.10%となり、33年ぶりの高水準を記録。さらに2025年春闘では5.25%と2年連続で5%台を達成し、34年ぶりの高水準となりました。政府も「構造的な賃上げ」を掲げ、最低賃金の引き上げも続いています。しかし、中小企業にとって、単純な基本給の引き上げは経営を圧迫する要因となりかねません。
ここで注目すべきが、退職金制度を活用した人件費の戦略的配分です。既存の退職金制度を見直し、その原資の一部を給与のベースアップに充てながら、新たに選択制退職金制度を導入するという手法があります。
選択制退職金制度なら、これまで見えにくかった会社の退職金負担を「給与」として一旦見える化し、従業員が自分のニーズに応じて「今の手取り」と「将来の退職金」のバランスを選択できます。賃上げを求める従業員には給与として、将来を重視する従業員には退職金として、それぞれのニーズに対応できる柔軟な制度設計が可能になります。
さらに、選択制による社会保険料負担の軽減効果も活用すれば、限られた人件費予算の中で、より効果的な処遇改善を実現できます。賃上げ要請に応えつつ、企業の持続可能性を確保する。退職金制度は、この難しいバランスを取るための有効な手段となります。
従業員の老後不安の増大と企業の役割
「老後2000万円問題」が社会的な議論を呼んでから数年。公的年金だけでは老後の生活に不安を感じる人が増え続けています。特に若い世代ほど、将来の年金受給額への不安は大きく、自助努力による資産形成の必要性を感じています。
企業の退職金制度は、この老後不安を軽減する重要な役割を担います。確定給付型の制度であれば元本が保証され、確実な老後資金の形成が可能です。また、企業が掛金を拠出することで、従業員単独では難しい計画的な資産形成を支援できます。
従業員が将来への不安なく働ける環境を整えることは、企業にとっても大きなメリットがあります。老後の心配から解放された従業員は、目の前の業務により集中でき、結果として企業全体の生産性向上につながるのです。
本記事で紹介した7つの選択肢
- 退職一時金制度:最も基本的でシンプル
- 確定給付企業年金(DB):給付額保証の安心感
- 確定拠出年金(DC):自己責任型の資産形成
- 中小企業退職金共済(中退共):国の支援制度
- 小規模企業共済:経営者・役員向け
- iDeCo+:従業員の自主性を尊重
- YUKINつみたてDBプラン:選択制で柔軟な対応
今こそ退職金制度を始めるべき理由
70.1%の中小企業がすでに退職金制度を導入している現在、制度がないことは採用面で大きなハンディキャップとなります。
退職金制度は、単なる福利厚生ではありません。これからの時代を生き抜くための、企業と従業員の新しい関係性を構築する戦略的な投資です。人材不足が深刻化し、働き方が多様化する中で、従業員に選ばれる企業となるために、今こそ退職金制度の導入を検討すべき時です。
しかし、いきなり大きな制度を導入する必要はありません。YUKINつみたてDBプランなら完全選択制で会社の掛金負担なし、中退共なら国の助成金を活用しながら始められます。
重要なのは、まず一歩を踏み出すこと。小さく始めて、企業の成長とともに制度を充実させていけばよいのです。
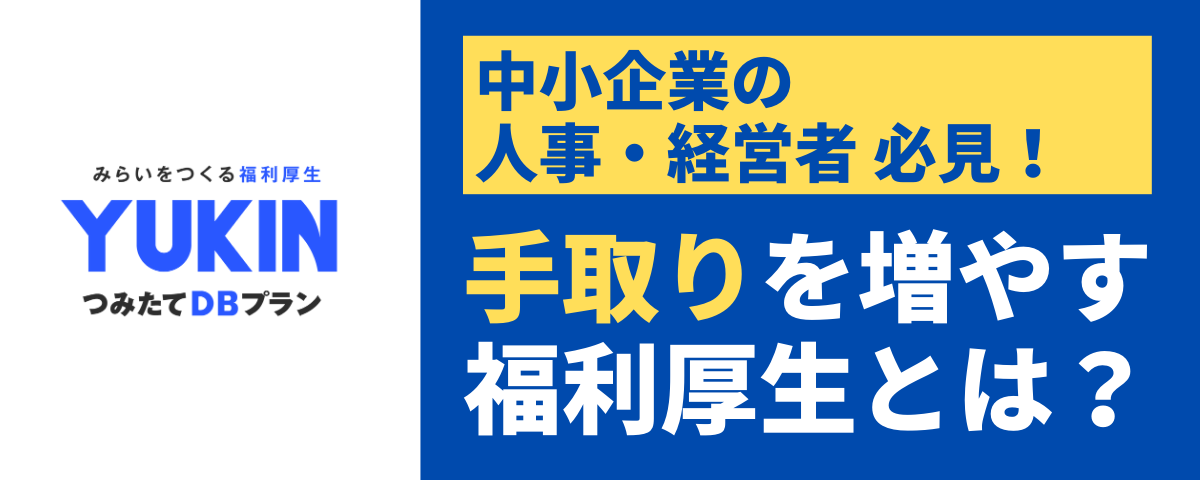
YUKINつみたてDBプラン
選択制退職金制度で従業員の資産形成を柔軟にサポート。企業の負担を抑えながら、従業員一人一人が自分に合った資産形成を選択できる制度です。