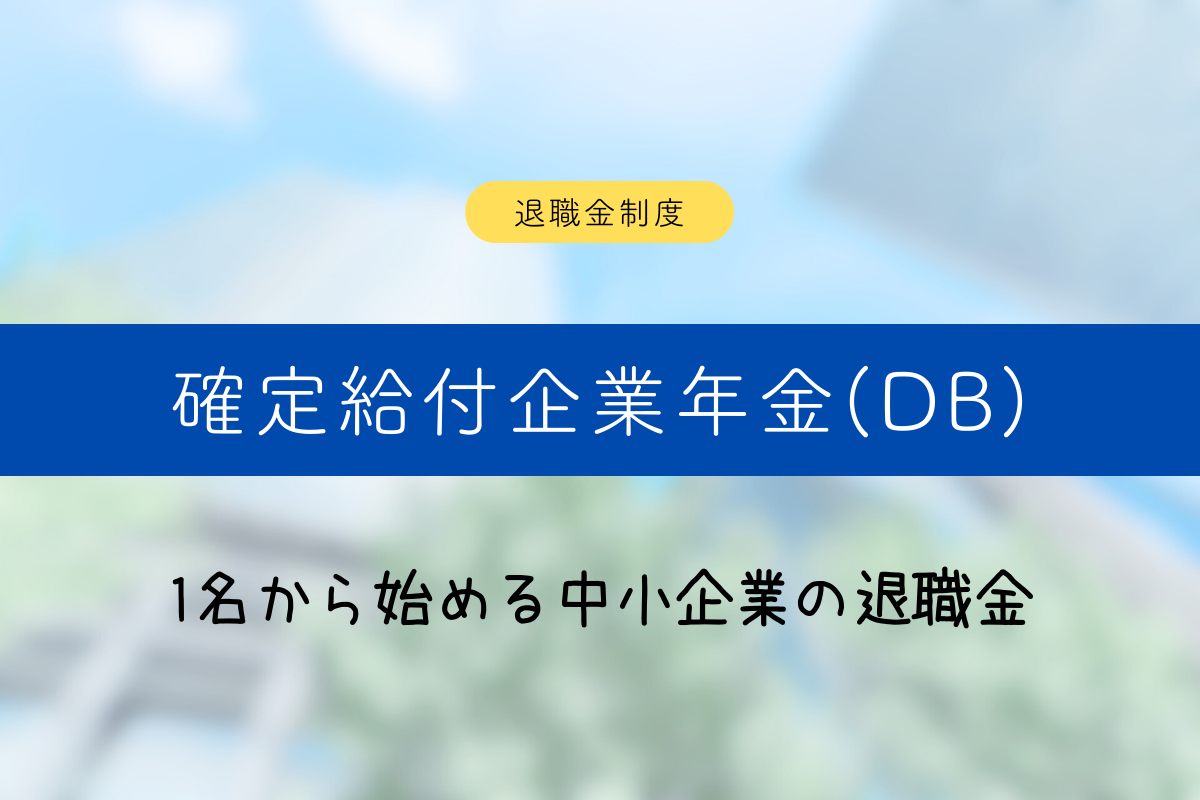確定給付企業年金(DB)とは?1名から始める中小企業の退職金
確定給付企業年金(DB:Defined Benefit)とは、従業員の将来の給付額をあらかじめ約束する企業年金制度です。中小企業にとって、運用リスクを企業が負う代わりに従業員には将来の受取額が保証されるため、安心感の高い退職金制度として注目されています。
従業員の定着率向上や採用力強化に効果があり、特に長期雇用を重視する中小企業での導入が進んでいます。また、選択制の確定給付企業年金なら1名から始めることができるため、小規模企業でも導入しやすい制度です。
企業の退職金制度全体については「中小企業の退職金制度完全ガイド」で詳しく解説していますが、この記事では確定給付企業年金に特化して、制度の成り立ちから具体的な仕組み、選択制DBまで分かりやすく解説していきます。
目次
確定給付企業年金の成り立ち|なぜ生まれた制度なのか?
実は、2000年代初頭の日本では、既存の退職金制度が深刻な問題を抱えて行き詰まっていました。
1961年から続いた適格退職年金制度は、誰が責任を持つのか曖昧で、従業員への情報開示もありませんでした。また、多くの制度で財政状況が悪化し、従業員の受給権保護が不十分な状態でした。
一方、厚生年金基金も大きな問題を抱えていました。国の年金の一部を代わりに運用する「代行部分」のリスクが重く、多くの基金で財政悪化が深刻化していました。後にAIJ投資顧問事件などの運用トラブルも明らかになりました。
こうした状況を受けて、政府は抜本的な制度改革に乗り出しました。適格退職年金制度は2012年3月末での廃止が決定され、厚生年金基金も新規設立停止の方向性が示されました。
そして2002年4月、これらの問題を解決する新しい制度として「確定給付企業年金法」が施行され、確定給付企業年金がスタートしました。責任の所在を明確にし、従業員への情報提供を義務化し、代行部分を廃止して純粋な企業年金とし、企業規模に関係なく導入しやすくしたのです。これにより、企業にとっては始めやすく、従業員にとっては安心できる制度になったんですね。
DB制度の種類と選び方|どのタイプが自社に合う?
確定給付企業年金には、運営の仕方によって3つのタイプがあります。どれを選ぶかで、管理の大変さや費用が大きく変わってきます。
規約型企業年金|オーダーメイドの企業年金制度
規約型は、自社で信託銀行や生命保険会社と直接契約して運営するタイプです。自社のニーズに合わせて細かく制度設計できるのが魅力ですが、その分、担当者が制度の専門知識を身につけて、日々の管理業務をこなす必要があります。
正直なところ、かなり手間がかかるので、人事部がしっかりしている大企業向けの制度と考えた方がいいでしょう。
基金型企業年金(総合型)|複数事業主で共同運営
基金型は、複数の企業が力を合わせて「企業年金基金」という組織を作って運営する方法です。全体で300名以上の加入者が必要ですが、1社あたりの人数制限はありません。
この方式の良いところは、基金の事務局がほとんどの手続きを代行してくれることです。制度設計もパターン化されているので分かりやすく、共同運営でコストも抑えられます。中小企業でも参加しやすいのが大きなメリットですね。
簡易型企業年金|とにかくシンプル
簡易型は、中小企業が簡単にDB制度を始められるよう作られました。給付の設計パターンを限定することで、導入手続きを簡単にし、運営費用も抑えています。
「複雑なことは考えたくないけど、DB制度は導入したい」という企業に適しています。
どのタイプを選ぶべき?
| 項目 | 規約型 | 基金型(総合型) | 簡易型 |
|---|---|---|---|
| 制度の自由度 | 高い(オーダーメイド) | 中程度(パターン型) | 低い(定型) |
| 管理の負担 | 重い | 軽い | 軽い |
| 運営コスト | 高い | 安い | 安い |
| 向いている企業 | 大企業 | 中小企業 | 小規模企業 |
| 担当者の専門性 | 一定の知識が必要 | 基本レベルでOK | 基本レベルでOK |
給付設計の基本|どんな受け取り方ができる?
DB制度では、退職時にどのくらい受け取れるかを事前に決めておきます。この「給付設計」は企業の考え方によって様々です。
一般的なのは、退職時の給与や平均給与をベースに計算する方法、人事評価を反映するポイント制などがあります。受け取り方も、年金として分割で受け取るか、一時金としてまとめて受け取るか選択できる制度が多いですね。
長く働いてもらいたい企業では、勤続年数が長いほど給付額が大きく増える設計にすることが多いです。これにより、従業員の定着率向上も期待できます。
資産運用の仕組み|お金はどう増やされる?
DB制度では、企業が毎月払う掛金を専門機関が運用して増やしていきます。運用は信託銀行や生命保険会社などのプロが行うので、従業員が投資について悩む必要はありません。
ただし、運用がうまくいかなかった場合のリスクは企業が負います。そのため、運用目標は現実的に設定することが大切です。一般的には、保守的で年2〜3%、標準的で年3〜4%、積極的で年4〜5%程度を目安にしています。
運用利回りが1%変わると、必要な掛金額も変わってしまうので、「高い収益を狙いすぎない」ことがポイントですね。
会計・税務の影響|実際の負担はどのくらい?
DB制度を導入すると、企業の財務諸表にも影響が出ます。将来の支払予定額(退職給付債務)と積立額(年金資産)の差が、貸借対照表に載ることになります。
ただし、税制面では大きなメリットがあります。払った掛金は全額、会社の経費として認められるため、法人税が安くなります。
実際の負担軽減例
- 従業員数:50名
- 月額掛金:1人あたり1万円
- 年間掛金:600万円(実際に支払う金額)
- 法人税軽減:約180万円(税率30%の場合)
- 実質負担:約420万円
つまり、600万円払っても実際の負担は420万円になるということです。ただし、最初に600万円は必要なので、その点は注意が必要ですね。
リスクと対策|何に気をつけるべき?
DB制度で最も怖いのは「積立不足」です。運用がうまくいかなかったり、金利が下がったりすると、将来の支払いに必要なお金が足りなくなることがあります。
企業は従業員に「○年働いたら○○万円支払う」と約束しているので、運用結果に関係なく、その約束は守らなければなりません。つまり、足りない分は企業が追加で払う必要があります。
その他にも、みんなが想定より長生きする長寿リスクや、物価上昇で給付額の価値が下がるインフレリスクなどもあります。
もし積立不足が起きたら、短期的には追加でお金を入れ、長期的には制度の見直しを検討します。ただし、すでに働いた分の給付は減らせないので、最初の制度設計が本当に大切になります。
企業・従業員のメリット・デメリット
企業にとってのメリット・デメリット
メリット
何といっても人材確保への効果が大きいですね。「将来の年金額が保証されている」という安心感は、求職者にとって魅力的です。同業他社との差別化にもなりますし、優秀な人材を獲得しやすくなります。
税制面でも、先ほどお話しした通り、実質的な負担を軽くできます(例:年間掛金600万円の場合、法人税軽減約180万円で実質負担約420万円)。
デメリット
最大の問題は、企業が運用リスクを背負うことです。「勤続30年なら退職金2000万円」のような約束をしているので、運用がうまくいかなくても、その約束は守らなければなりません。積立が足りなくなったら、企業が補填する義務があります。
また、制度運営には継続的に費用がかかります。数理計算や資産管理、記録管理など、企業規模によっては年間数百万円の運営コストが必要になることもあります。
従業員にとってのメリット・デメリット
メリット
従業員にとっては「安心感」が最大のメリットです。将来もらえる年金額が事前に決まっているので、老後の生活設計を立てやすいですし、市場がどんなに荒れても、約束された金額は確実に受け取れます。
個人ではできないような専門的な資産運用の恩恵も受けられますし、税制優遇も大きいです。特に「退職所得控除」は魅力的で、勤続年数に応じて大きな非課税枠があります。
退職所得控除の計算
- 勤続20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)
- 勤続20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
例えば勤続30年なら、1,500万円まで税金がかかりません。これは大きいですよね。
デメリット
投資に興味がある人には、「自分で運用先を選べない」のがもどかしいかもしれません。専門機関任せなので、「もっと積極的に運用したい」と思っても自分ではできません。
また、給付額が名目で固定されているため、長期的なインフレで実質的な価値が目減りするリスクもあります。年2%のインフレが30年続けば、受取時の価値は現在の半分程度になってしまいます。
メリット・デメリット まとめ表
| 立場 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 企業 | ・人材獲得・定着効果 ・税制優遇で実質負担軽減 ・企業価値向上 | ・運用リスク(約束履行義務) ・継続的な運営コスト ・制度変更の困難さ |
| 従業員 | ・将来の安心感 ・プロによる資産運用 ・退職所得控除の大幅優遇 | ・運用方法を選べない ・インフレによる価値減少リスク |
新しい選択肢|選択制DB(YUKINつみたてDBプラン)
従来のDB制度の課題を解決する新しい方法として、「選択制DB」が注目されています。中でも「YUKINつみたてDBプラン」は、中小企業でも導入しやすいよう工夫された制度です。
選択制DBって何が違うの?
従来のDB制度は、企業がお金を出して、全員強制加入でした。でも選択制DB(YUKIN)は、従業員が自分の給与の一部を使って、希望者だけが加入できます。
これにより、企業は新しくお金を出す必要がなくなりますし、従業員も「今の手取りを重視したい」「将来の備えをしたい」など、自分のライフスタイルに合わせて選択できるようになりました。
YUKINつみたてDBプランの特徴
YUKINが他と大きく違うのは、従来のDBの最大の弱点である「積立不足リスク」への対策が最初から組み込まれていることです。一般勘定100%運用とキャッシュバランスプランにより、企業が予想外の追加負担を背負うリスクを大幅に軽減しています。
YUKINの柔軟さ
- 1名から導入できる
- 役員・経営者も加入OK(70歳未満)
- 月1,000円から最大30万円まで、給与の20%以内で設定
- 年1回、拠出額の変更可能
利用イメージ 例えば5名の会社なら、こんな使い方ができます:
- 社長:月30万円
- 従業員A:月1万円
- 従業員B:月5,000円
- 従業員C・D:拠出しない(現在の手取り重視)
社会保険料の軽減効果について
選択制では、拠出分だけ給与が下がる仕組みになっています。そのため、社会保険料の計算基準となる標準報酬月額も下がり、結果的に会社と従業員の両方の社会保険料負担が軽くなります。
軽減効果の例
- 月給30万円の人がDB拠出2万円を選択
- 標準報酬月額:30万円→28万円
- 社会保険料軽減(会社+本人):月約6,000円、年間約7万円
ただし、これは選択制の仕組みにより発生する副次的な効果です。標準報酬月額が下がることで、社会保障給付にも影響しますので、従業員には丁寧な説明が必要となります。
従来DBとの比較
| 項目 | YUKIN | 従来のDB |
|---|---|---|
| 会社の負担 | 選択制なら不要 | 掛金負担あり |
| 加入 | 任意 | 強制 |
| 最低人数 | 1名から | 実質20名程度 |
| 役員加入 | 可能 | 可能 |
| 社会保険料 | 軽減あり | 軽減なし |
| 積立不足リスク | 対策済み | 企業が負担 |
こんな企業におすすめです
YUKINが向いている企業
- 小規模から中規模の企業
- 役員・経営者も含めて制度を作りたい企業
- 従業員の価値観を尊重したい企業
- 従業員の手取り向上と将来の資産形成を両立したい企業
- 人件費を抑えながら退職金制度を始めたい企業
まとめ|自社に合った退職金制度を選ぼう
確定給付企業年金(DB)は、従業員に「将来の安心」を提供できる制度です。企業にとっては人材確保と税制優遇、従業員にとっては確実な老後資金と大幅な税制優遇(特に退職所得控除)というメリットがあります。
従業員50名以上で経営が安定している企業、長期雇用を大切にする企業には特に向いています。一方、従業員数の変動が大きい企業や成長途中の企業では、慎重に検討した方がいいでしょう。
従来のDB制度が合わない企業でも、「選択制DB」のYUKINつみたてDBプランなら、1名から始められて、会社の新しい負担もなく、積立不足のリスクも軽減されています。
退職金制度は従業員との大切な約束です。自社の状況をよく考えて、最適な制度を選んでくださいね。
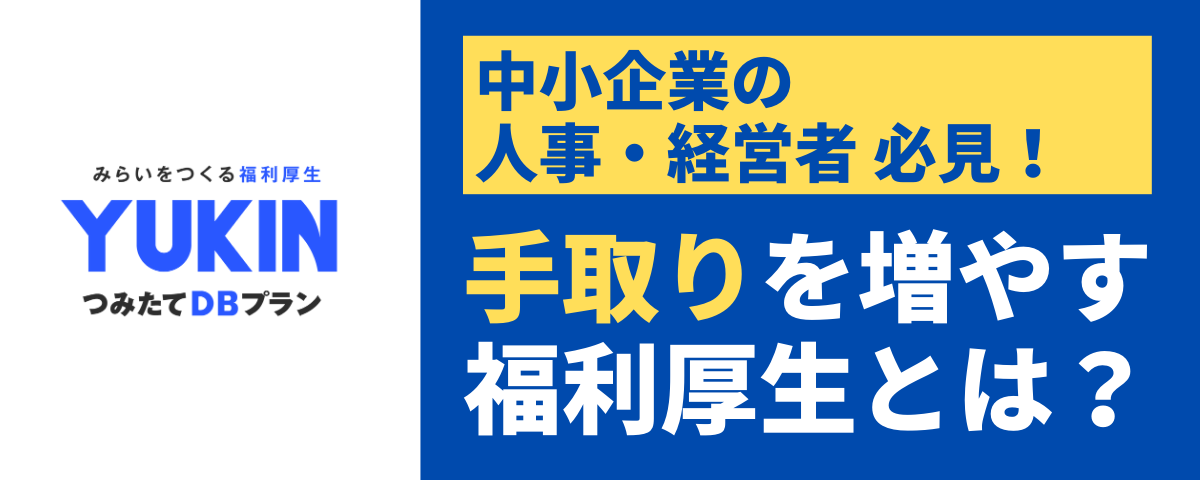
YUKINつみたてDBプラン
選択制退職金制度で従業員の資産形成を柔軟にサポート。企業の負担を抑えながら、従業員一人一人が自分に合った資産形成を選択できる制度です。
よくあるご質問
確定給付企業年金(DB)とは何ですか?
確定給付企業年金(DB)とは、会社が従業員に対し、退職後の年金として将来受け取る金額をあらかじめ約束する制度です。給付額は給与や勤続年数などに基づいて決まります。
確定拠出年金(DC)とはどう違うのですか?
確定給付企業年金(DB)は会社が将来の年金額を保証し、運用も会社が行います。一方、確定拠出年金(DC)は会社が掛金を出すだけで、従業員自身が運用を行い、将来の受取額は運用成績によって変わります。
確定給付企業年金(DB)を導入する会社側のメリットは何ですか?
会社が確定給付企業年金(DB)を導入するメリットは、従業員に退職後の安心感を提供することで、優秀な人材を確保し、長く会社に定着してもらいやすくなる点です。また、会社が拠出した掛金は税務上の損金として認められるため、税負担を軽減する効果もあります。
従業員にとっての確定給付企業年金(DB)のメリットは何ですか?
従業員にとってのメリットは、将来受け取れる年金額があらかじめ決まっているため、老後の生活設計が立てやすいことです。また、年金資産の運用は会社が行うため、従業員自身が投資のリスクを負う必要がない点も安心です。
確定給付企業年金(DB)の運用にはどんなリスクがありますか?
確定給付企業年金(DB)では、会社が年金給付を保証するため、市場の変動や金利の状況によって運用成績が悪化した場合、会社が追加で積立を行うなど、財務上の負担や運用リスクを負う可能性があります。
確定給付企業年金(DB)の掛金や受け取る年金には税金がかかりますか?
会社が拠出する掛金は、税務上、会社の損金として認められます。従業員が退職後に年金として受け取る場合は雑所得として、一時金として受け取る場合は退職所得として課税されます。退職所得には税制上の優遇措置があります。
確定給付企業年金(DB)を導入する際、会社は何をすればいいですか?
確定給付企業年金(DB)を導入するには、まず会社の財務状況や従業員のニーズを調査し、最適な年金制度を設計します。その後、年金規約を作成して厚生労働省の承認を得る手続きが必要です。従業員への丁寧な説明と合意形成も重要になります。中小企業の場合は、総合型確定給付企業年金基金への編入も比較的簡単な導入方法として検討できます。